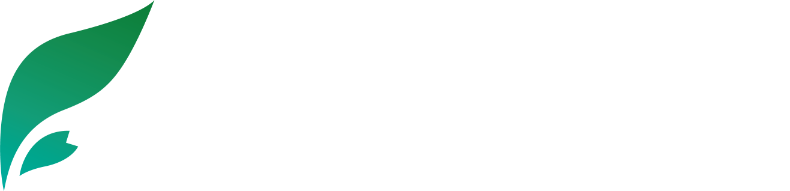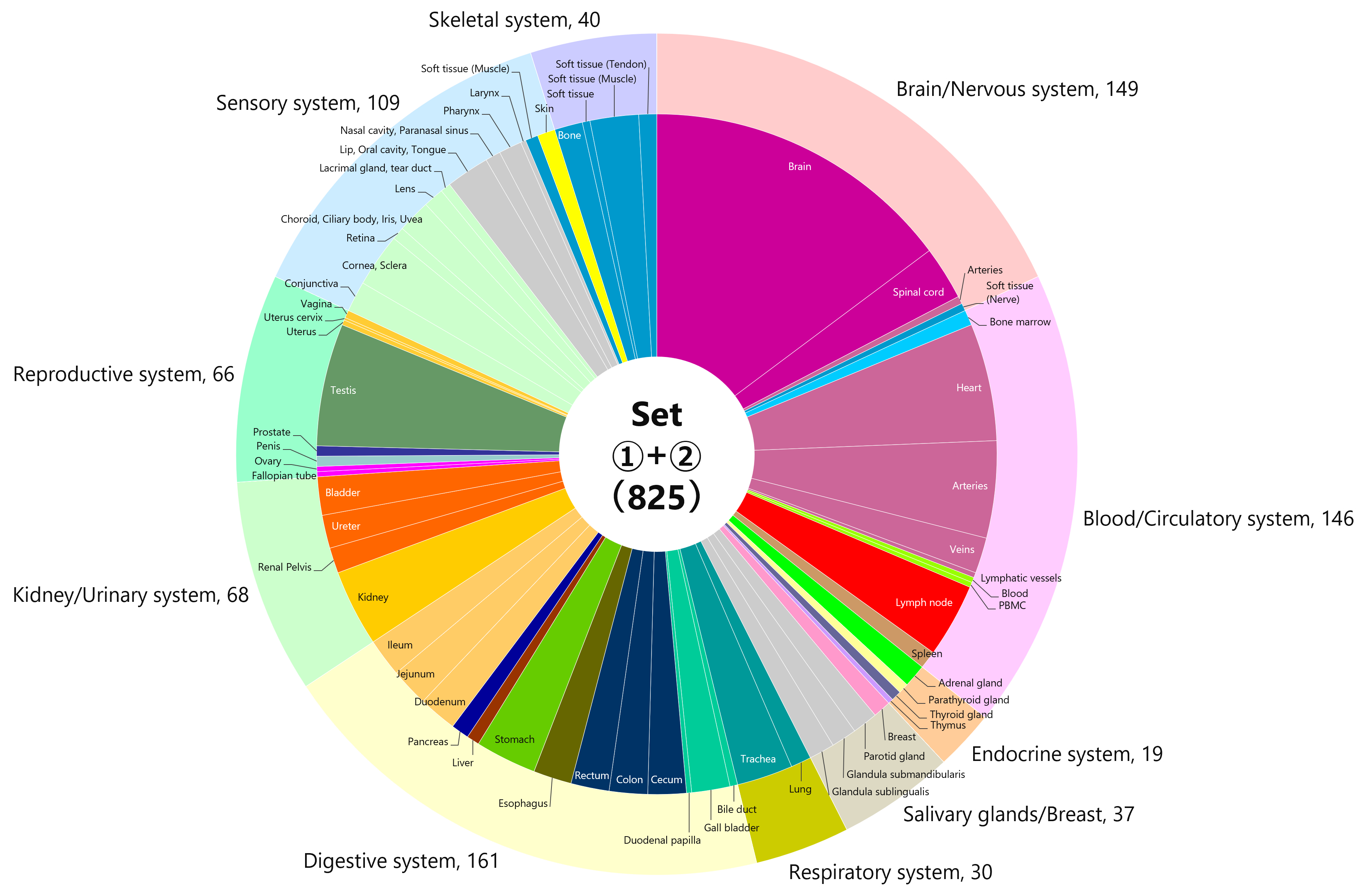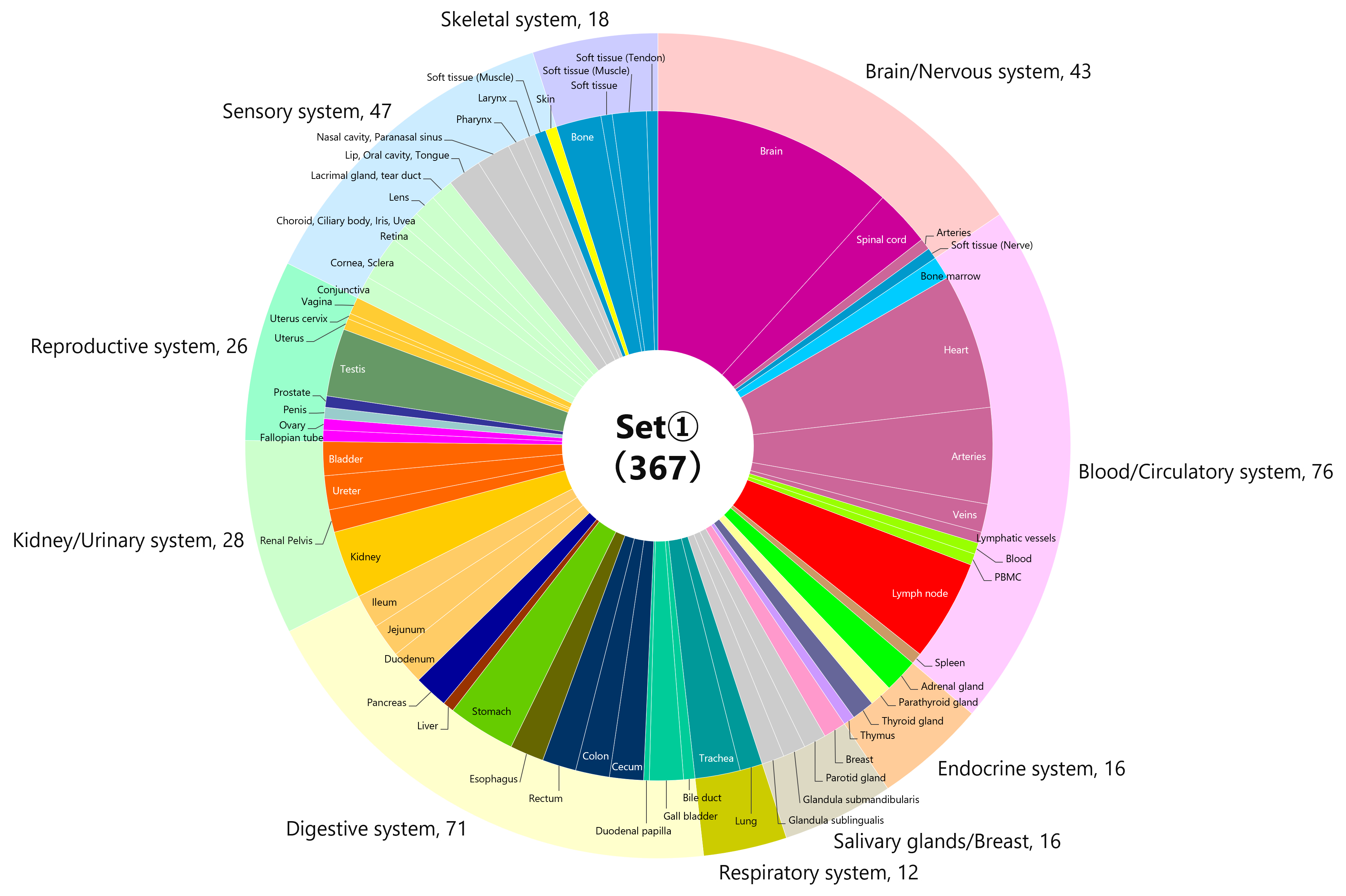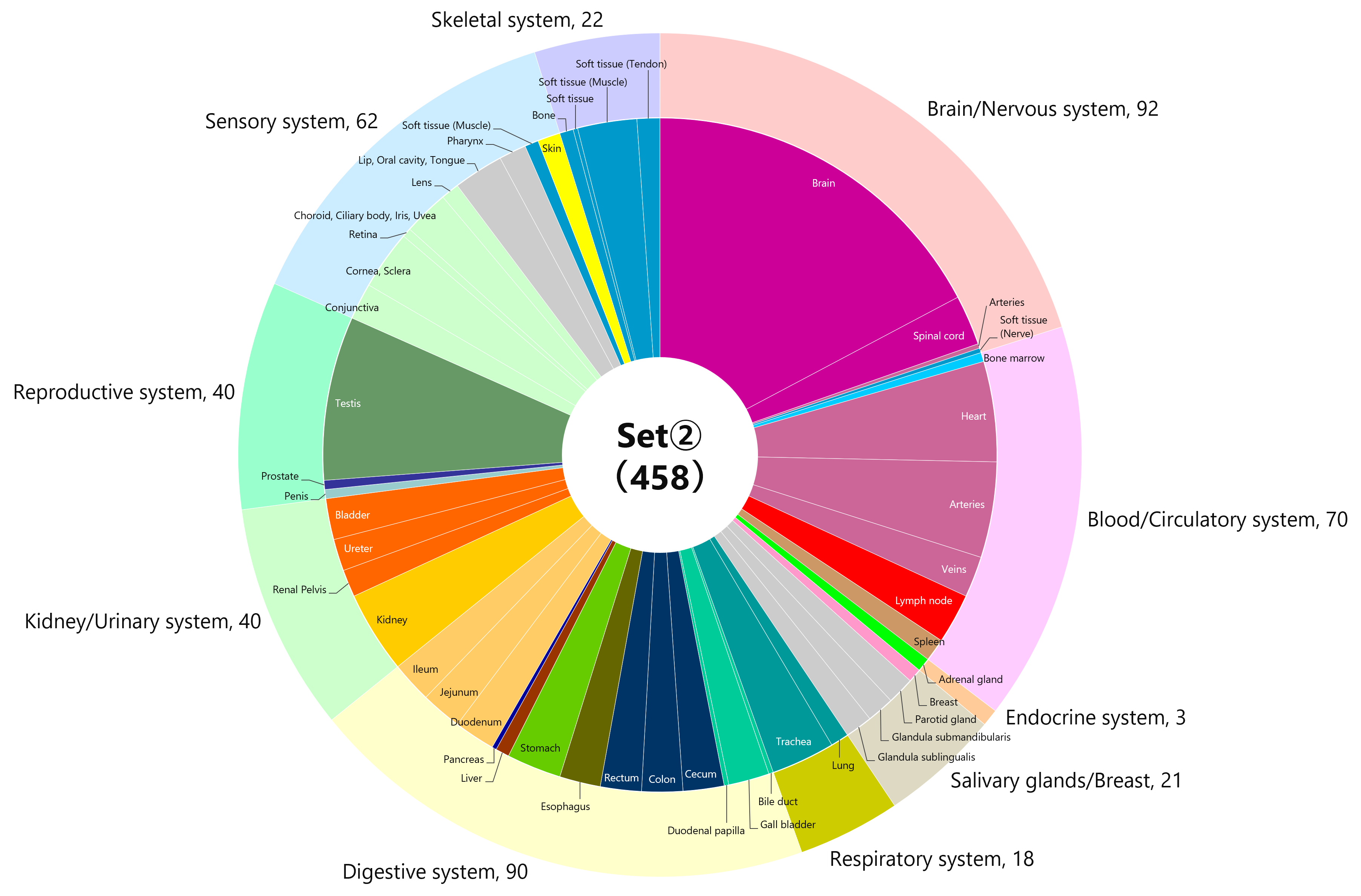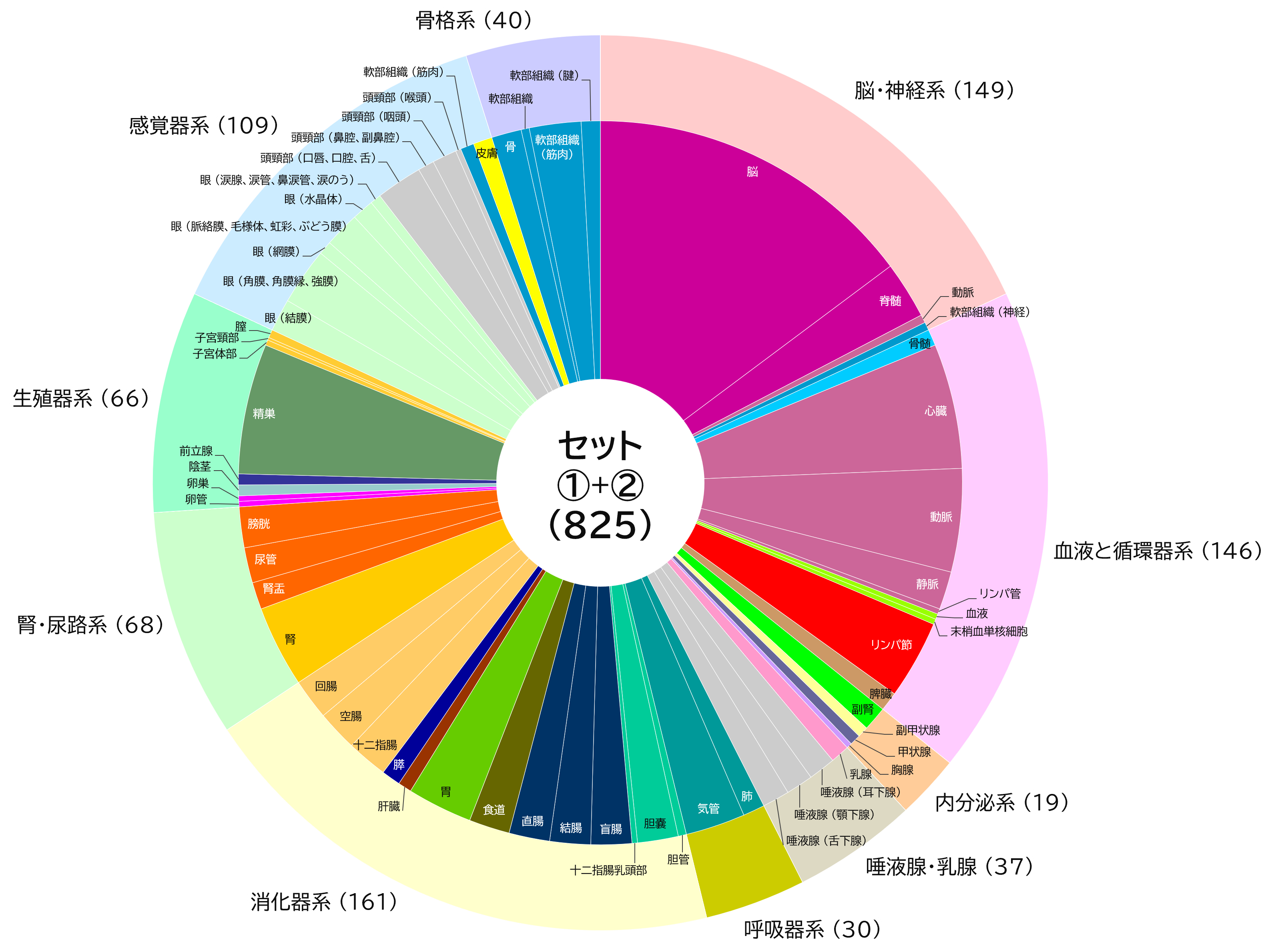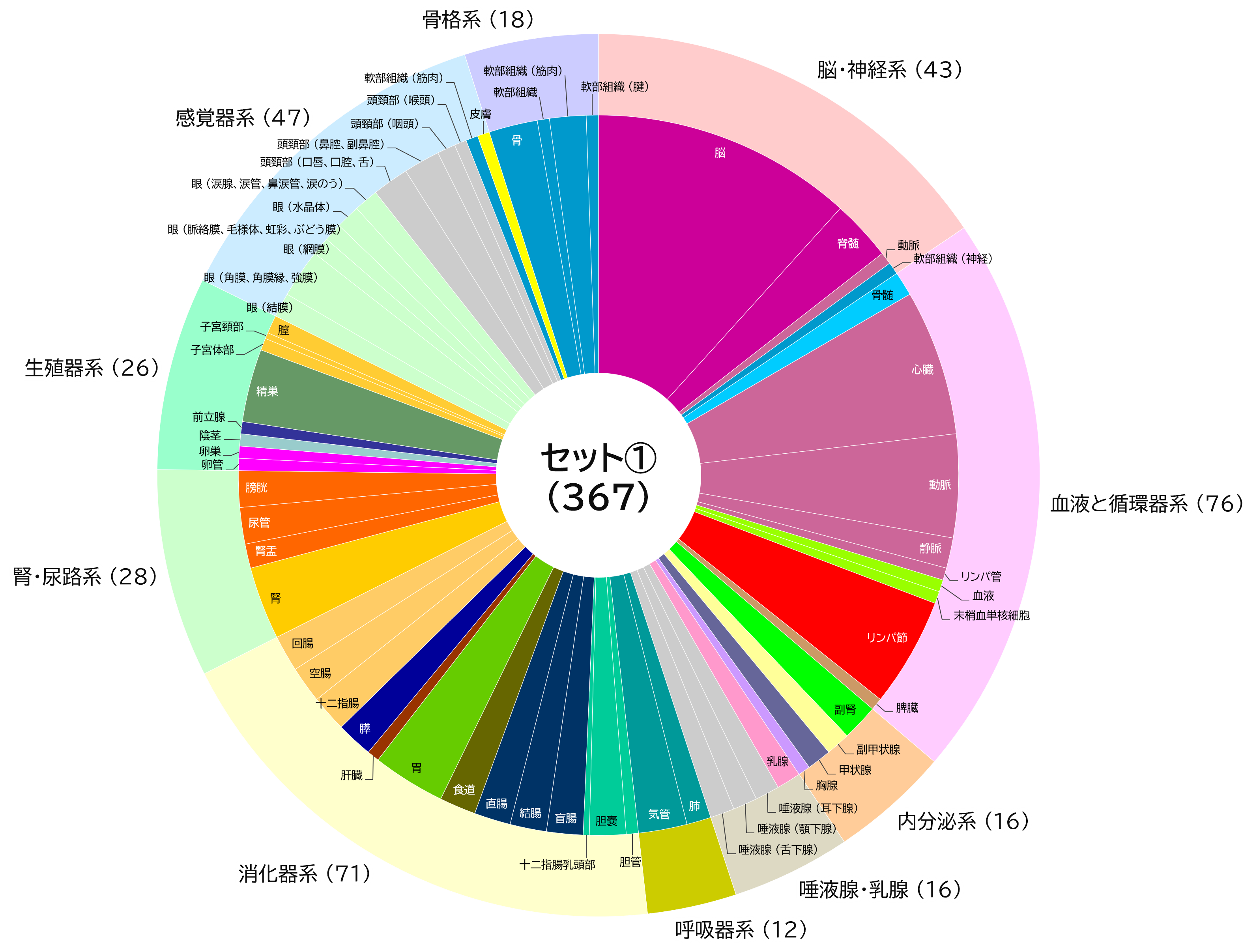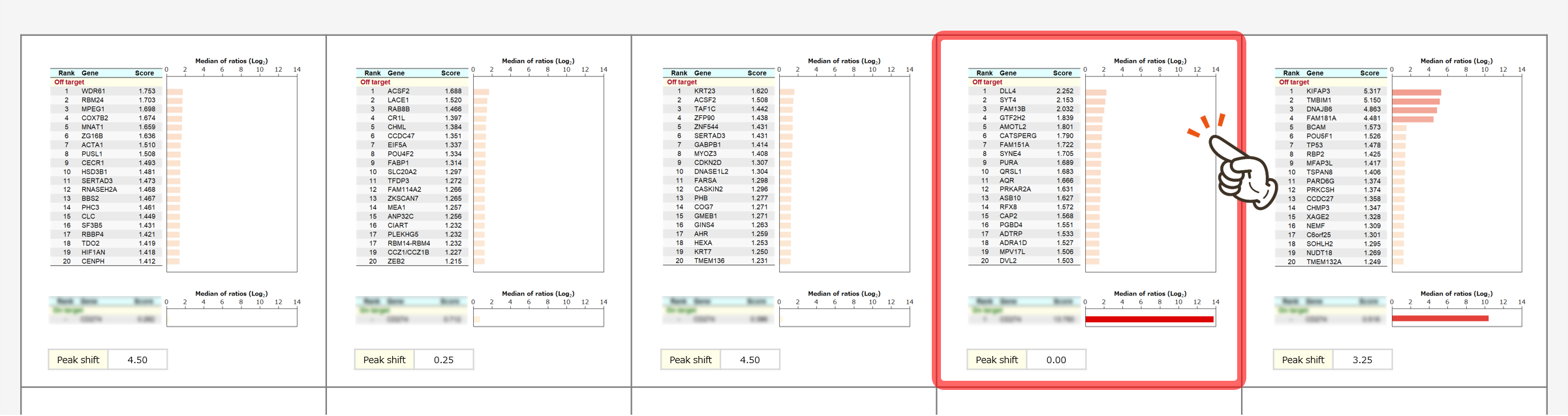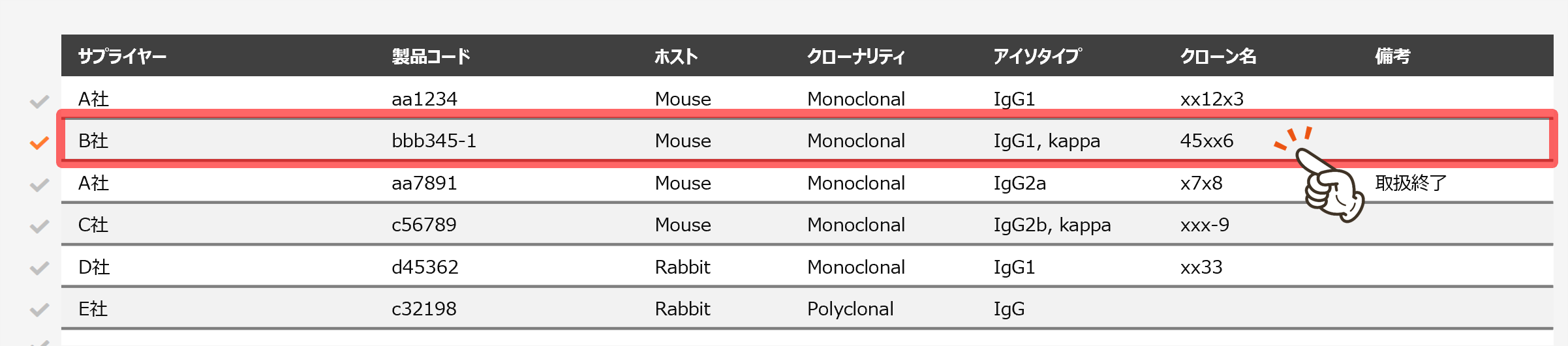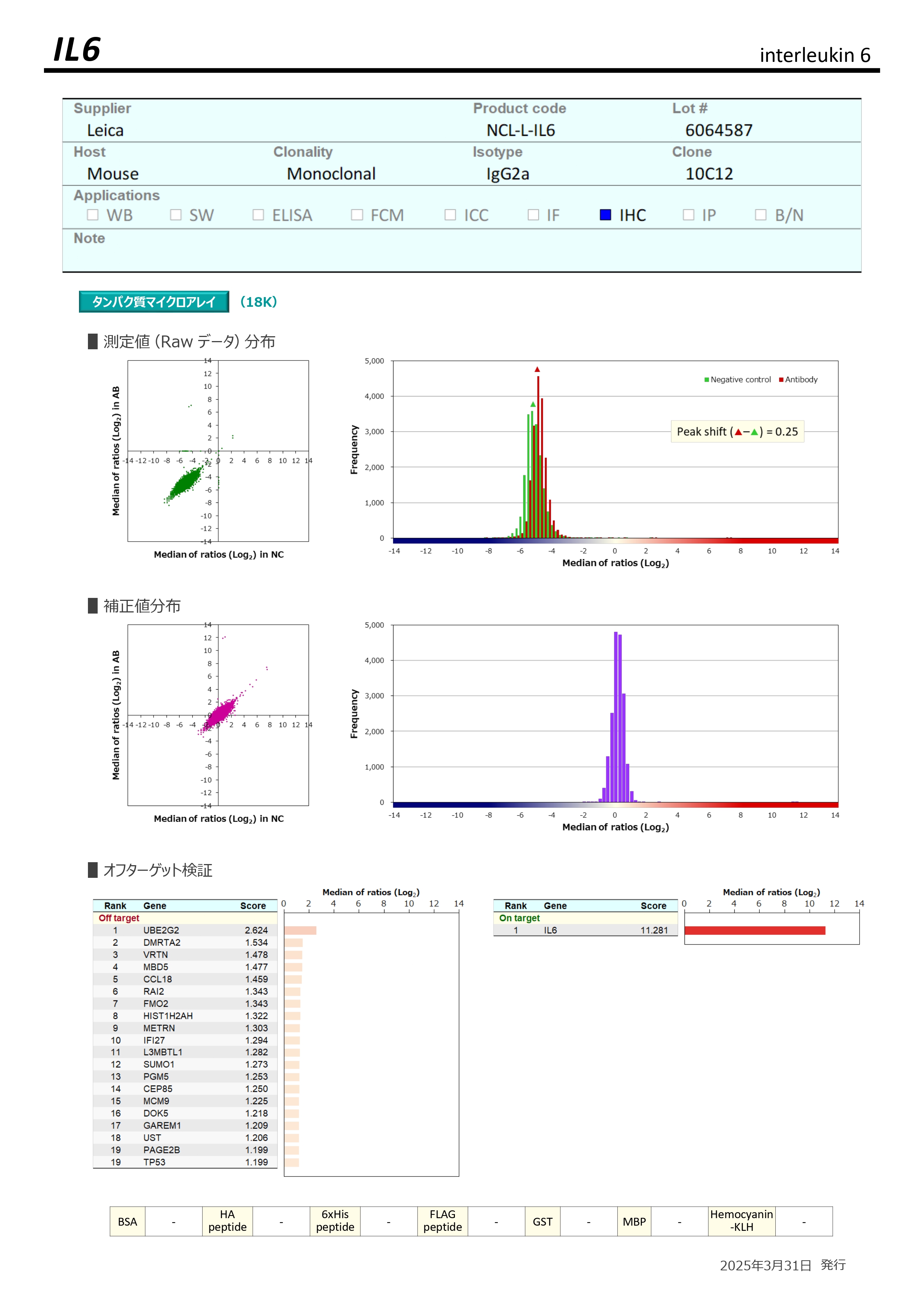こんにちは!
第15回で、実際に行った肺がん細胞株の遺伝子発現解析についてお話しました。クラスタ解析の結果、肺がん細胞株を小細胞がんと非小細胞がんの2つのグループに分けることができ、小細胞がんと非小細胞がんを区別する遺伝子があることがわかりました。治療するうえで非常に重要な小細胞がんと非小細胞がんの区別が遺伝子の発現データでできるということが、私の中ではちょっとした驚きでした。がんの性質と特定の遺伝子の発現が関連しているということを実感したのです。
けれども、実際は完全完璧に小細胞がんと非小細胞がんを区別できたわけではありませんでした。小細胞がんの約90%が含まれた小細胞がんのグループに、非小細胞がんのうちのカルチノイドや大細胞神経内分泌がんなども少し含まれたのです。ここで前回お話した肺がんの新しい分類を思い出して下さい。新しい肺がんの分類では、カルチノイドと大細胞神経内分泌がんは小細胞がんと同じ神経内分泌腫瘍に含まれます。クラスタ解析でのグループ分けで、小細胞がんのグループにカルチノイドや大細胞神経内分泌がんが含まれたことは、新しい肺がんの分類が遺伝子発現データでも裏付けられたといえるのではないかと思います。
また、クラスタ解析の結果、小細胞がんの約10%は非小細胞がんのグループに含まれました。この結果から言えることは、非小細胞がんのグループに含まれた小細胞がんは、非小細胞がんに似た遺伝子発現をしているということです。もしかしたら、すべての小細胞がんが同じ性質ではないのかもしれません。小細胞がんは進行がとても速く、転移や再発もしやすい厄介な性質をもつがんですから、もしも小細胞がんの中に非小細胞がんのような性質をもつものがあるのであれば、それは患者さんにとって良いことと言えるかもしれません。こういうタイプのがんだからと決めつけるのではなく、患者さん一人一人のがんの性質を調べてみることが大切だと感じました。
次回は、いったん解析の話からはなれて、上皮組織についてお話します。