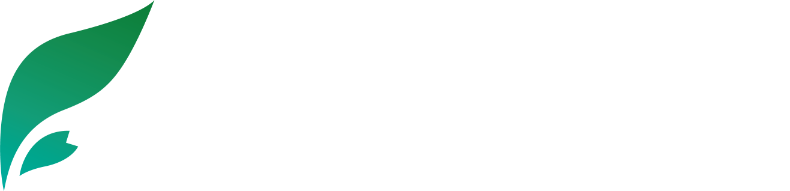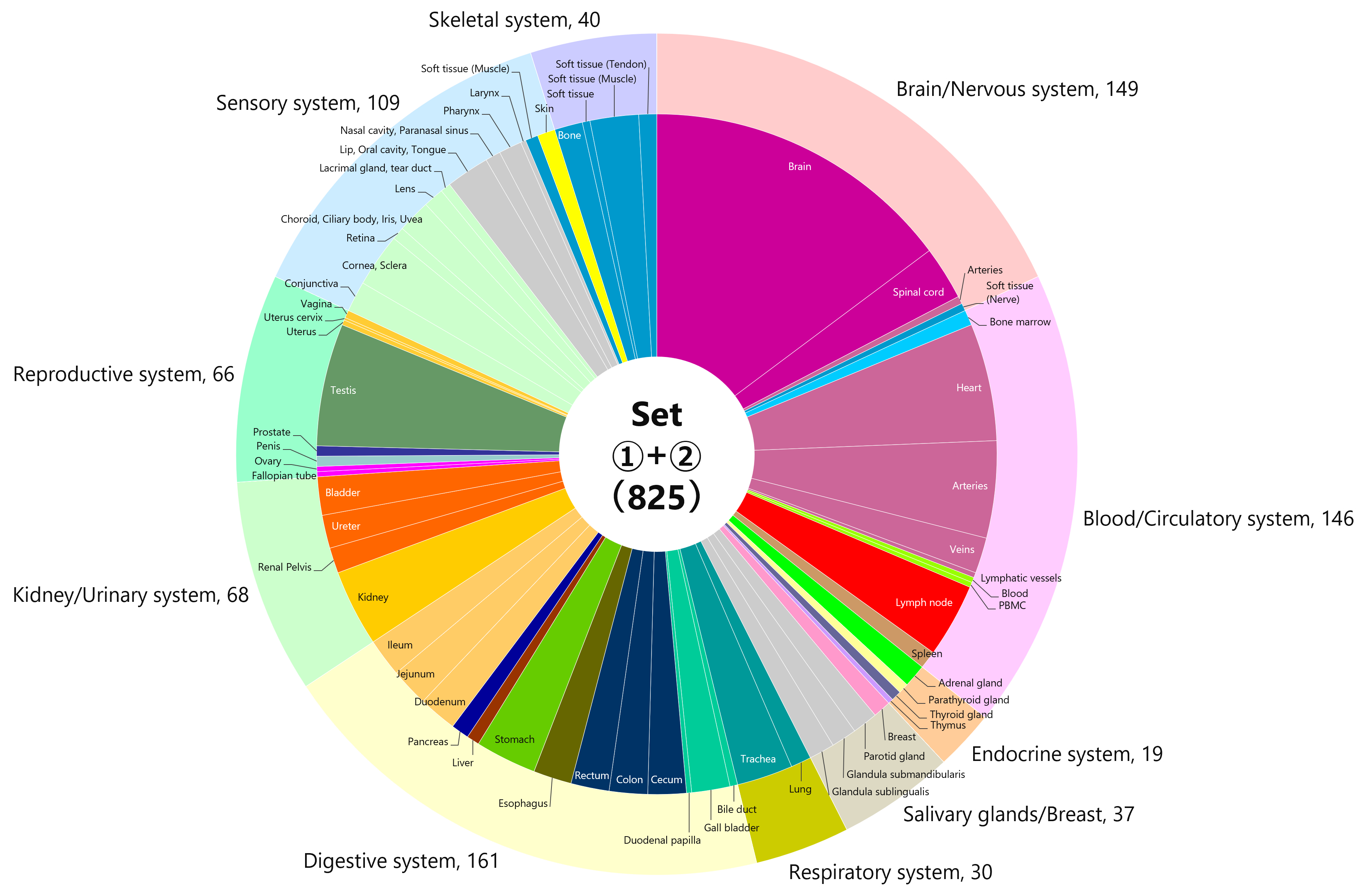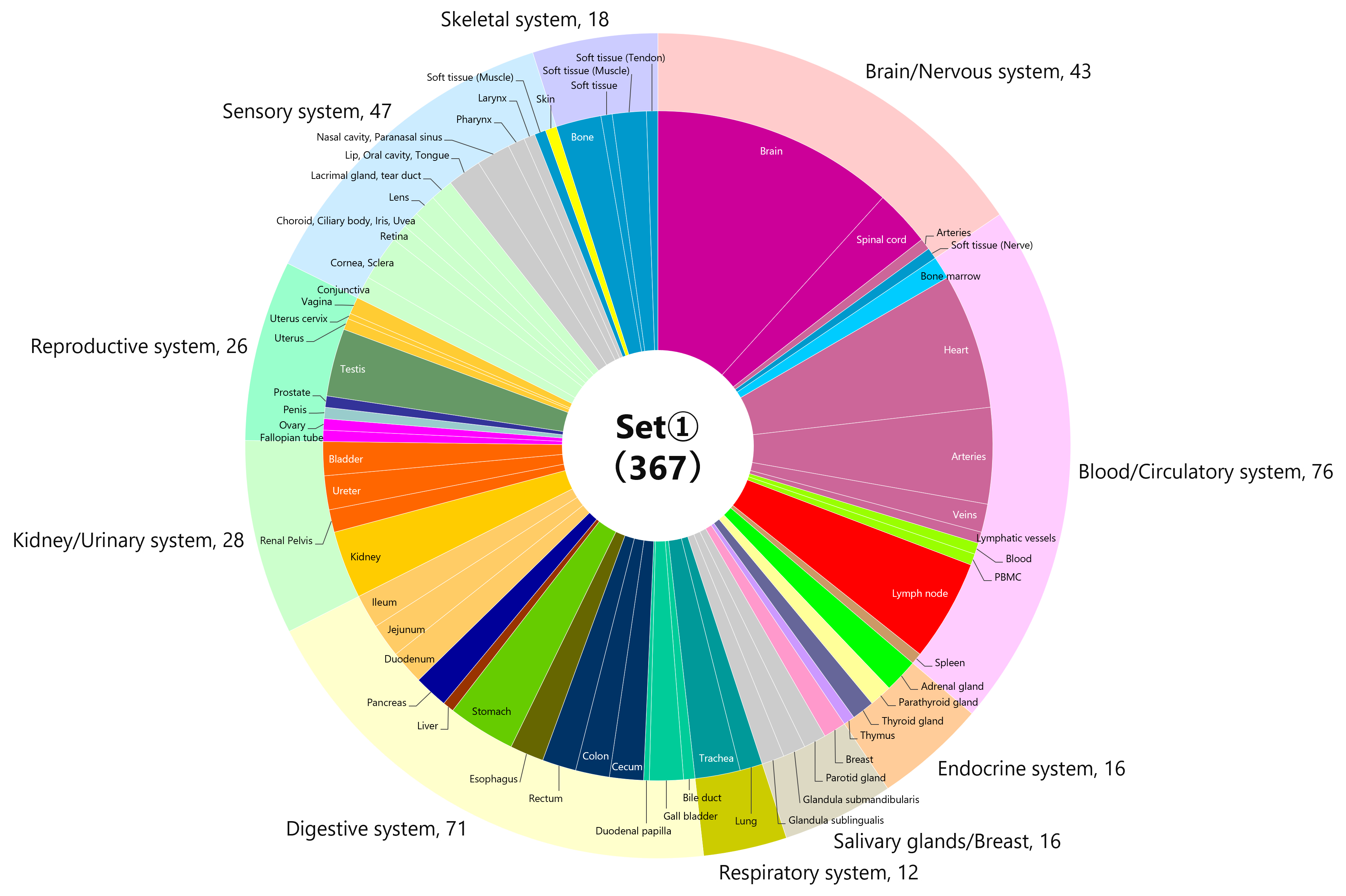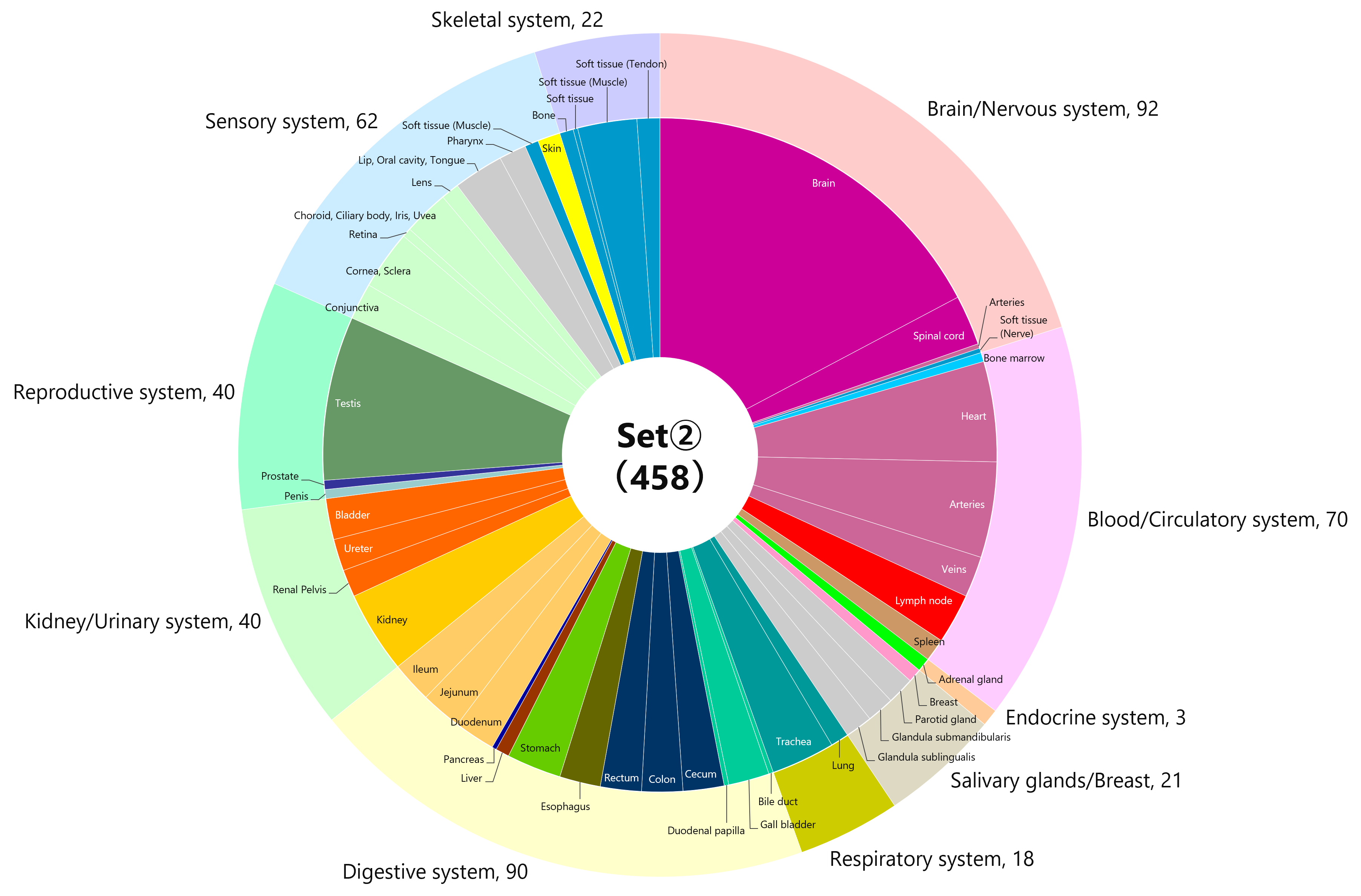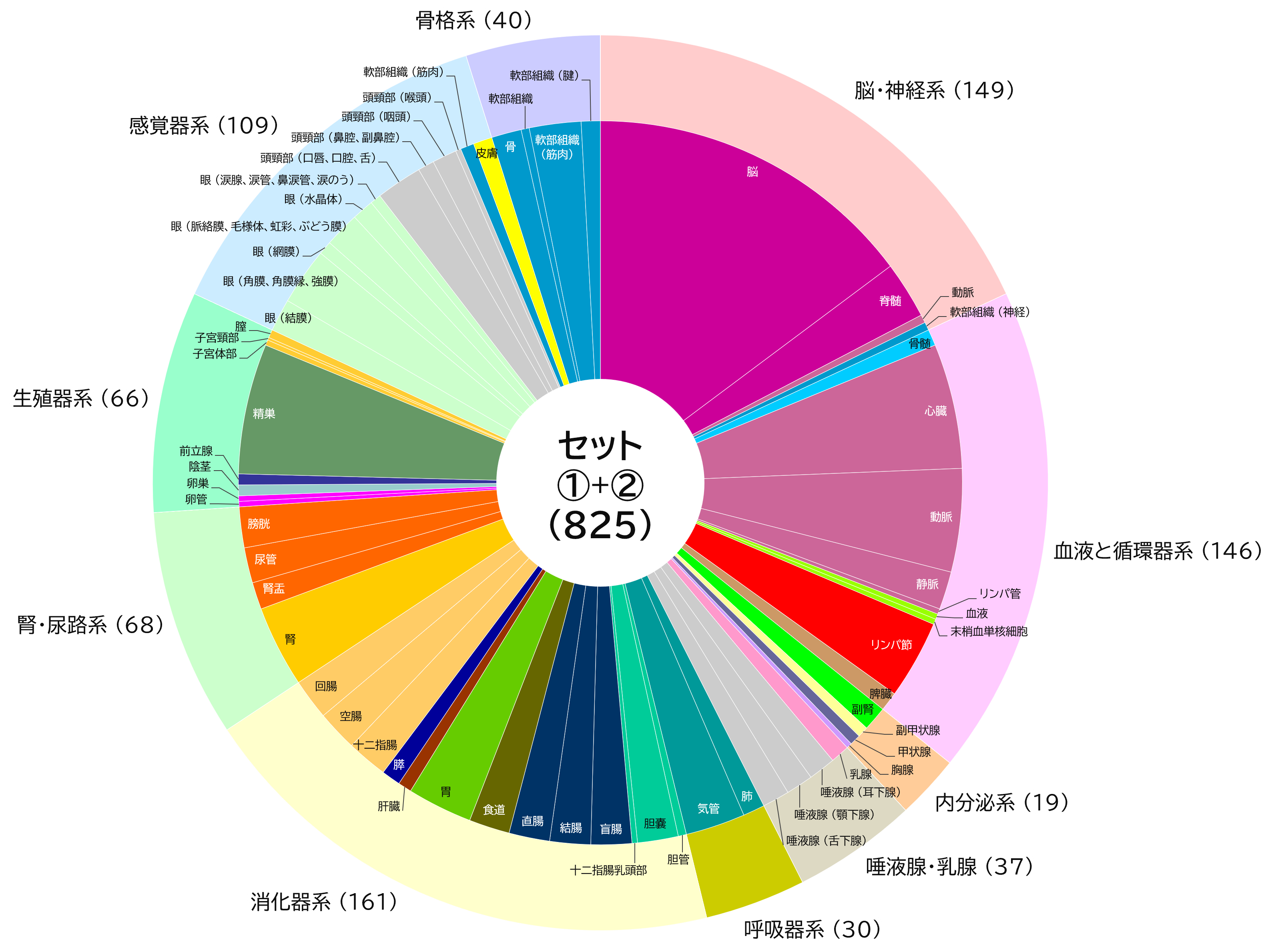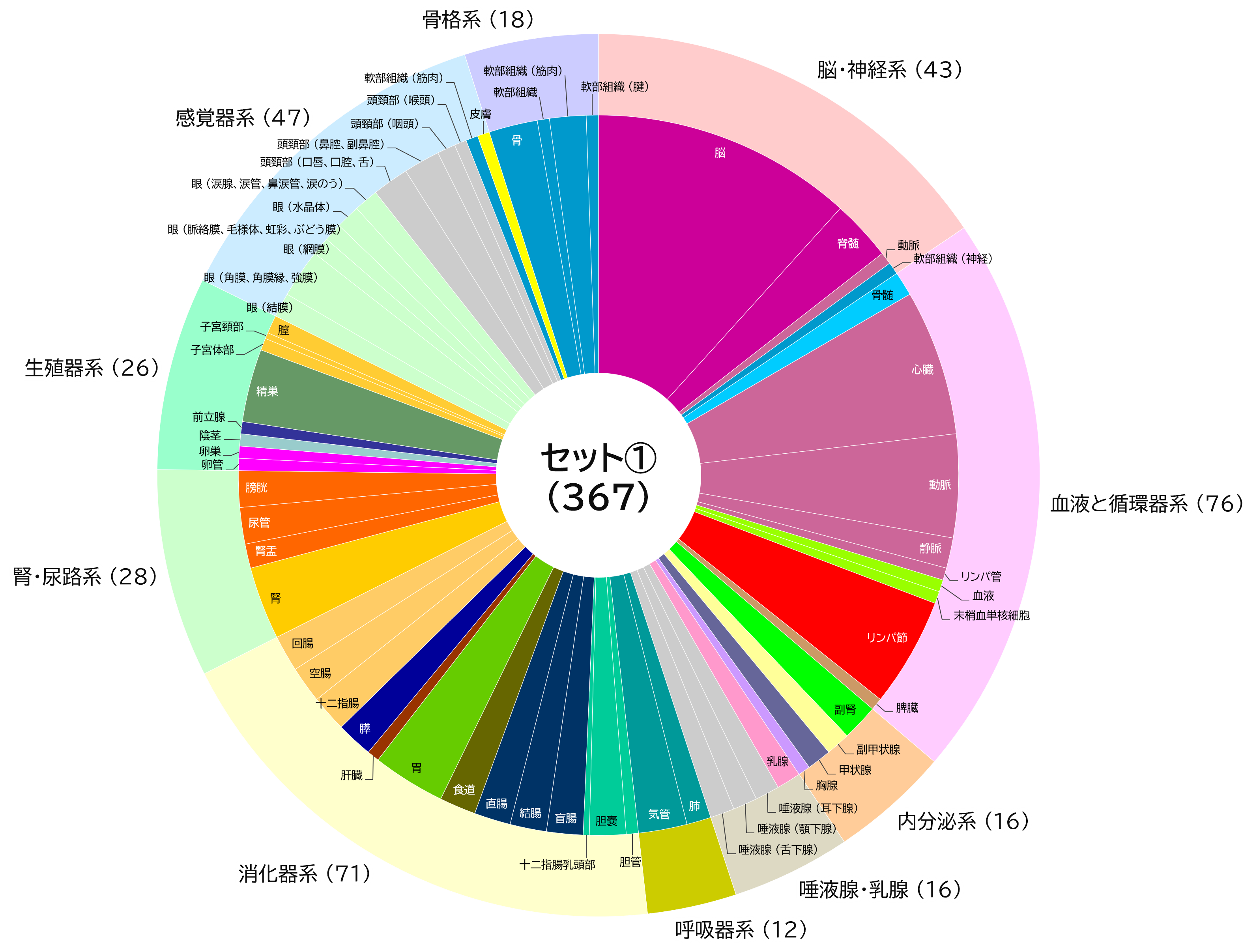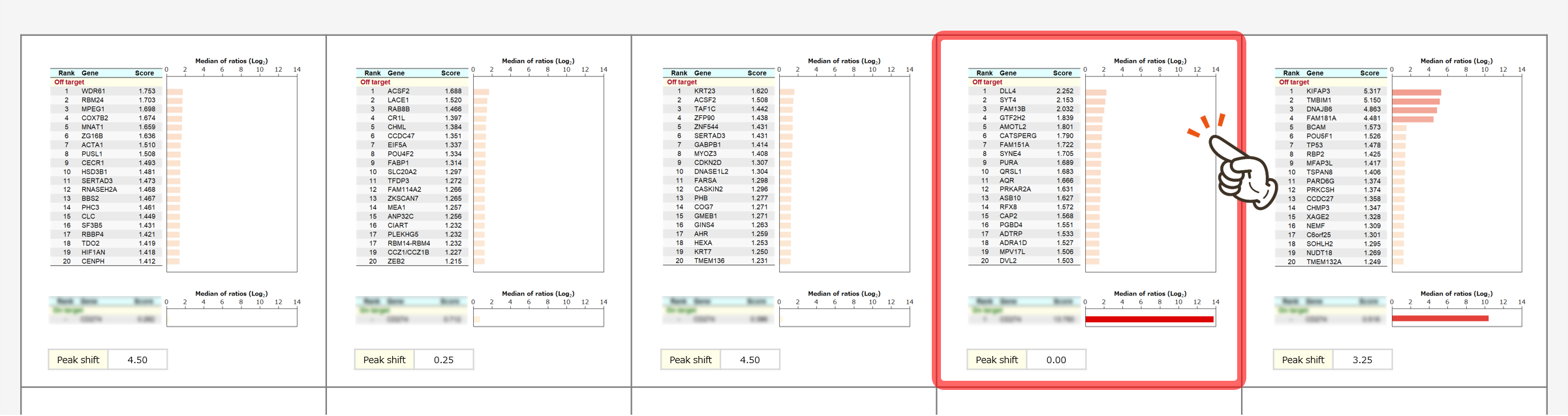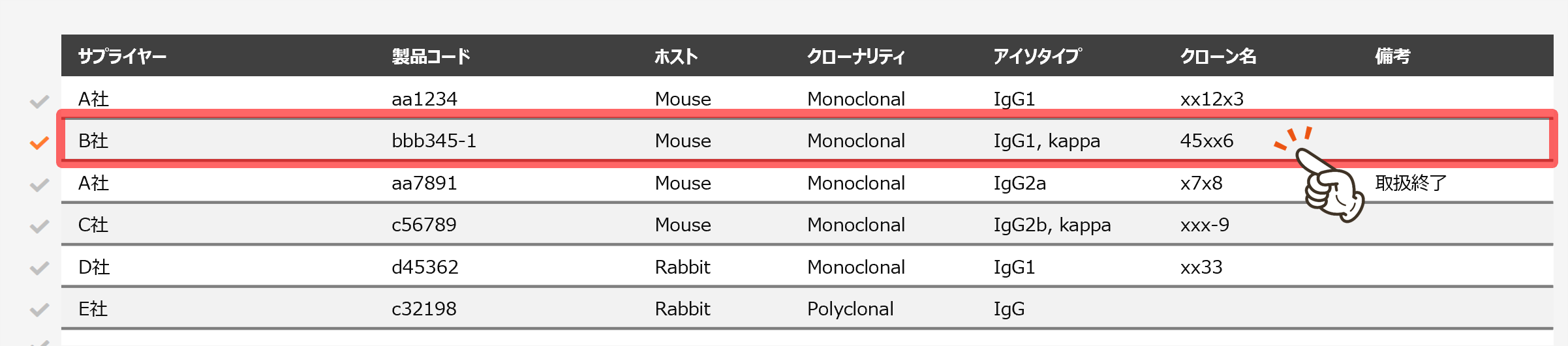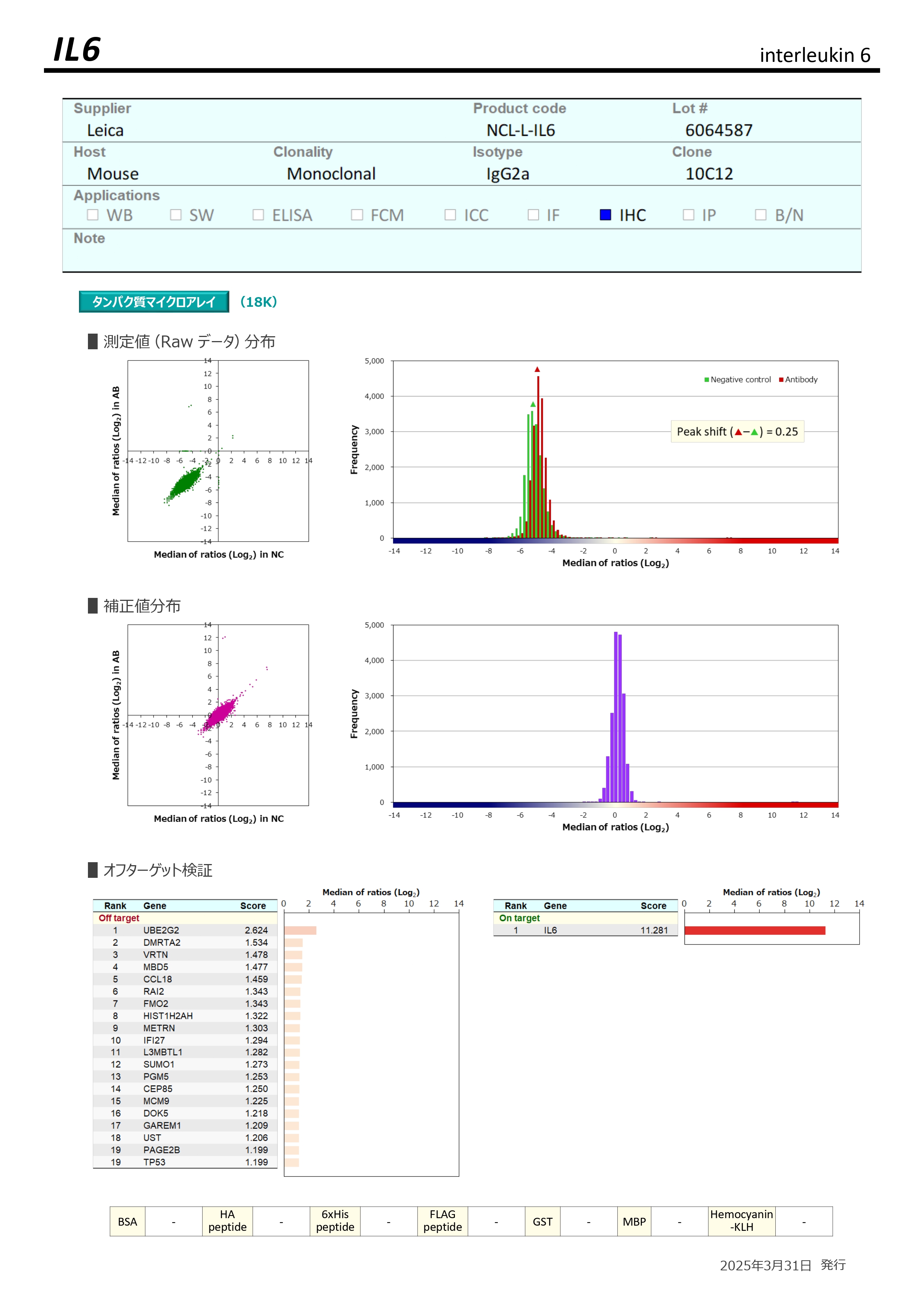こんにちは!
前回、細胞の中にある核に遺伝子の情報となるDNAが含まれているというお話をしました。今回はDNAについて、もう少し詳しくお話します。
DNAはヌクレオチドとよばれる基本単位が結合した鎖状の分子です。ヌクレオチドはリン酸、糖、塩基という3つの部分からなります。リン酸と糖が交互に結合したものがDNAの骨格となり、塩基は骨格から飛び出した形になっています。
塩基にはアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類があります。塩基には特定の塩基としか結合しない、相補性という重要な性質があります。必ずAはTと、CはGと結合してペアになります。このペアを塩基対とよびます。AとT、CとGの塩基対が形成されることで、DNAは基本的に2本鎖になっています。2本鎖になっていることでDNAはより安定しています。また、相補的な塩基対を利用し、遺伝情報を正確に複製することが可能です。一方の鎖に損傷があった時にはもう一方の鎖を鋳型として修復することもできます。
前回、核の中のDNAの長さをすべて足し合わせると約2メートルになるとお話しました。2メートルにもなるDNAにはものすごい数のヌクレオチドがつながっていることが想像できます。ヌクレオチドがたくさんつながると4種類の塩基が様々な順番で並ぶことになります。この塩基の並び順を塩基配列とよび、これが遺伝情報となっているのです。
目や肌の色、身長、血液型などの生物が持つ特定の特徴や性質のことを形質といいます。私たちの体の多くの形質はタンパク質によって決まっています。遺伝子は特定のタンパク質を作るための設計図のようなもので、その設計図はDNA内の特定の塩基配列として保持されています。
次回は、タンパク質が作られる仕組みについてお話します。