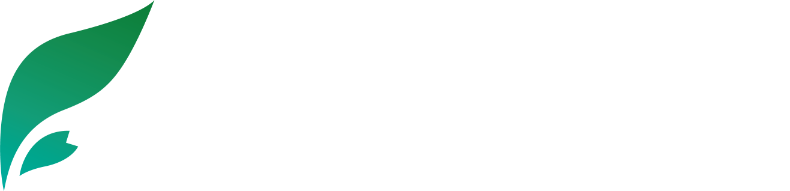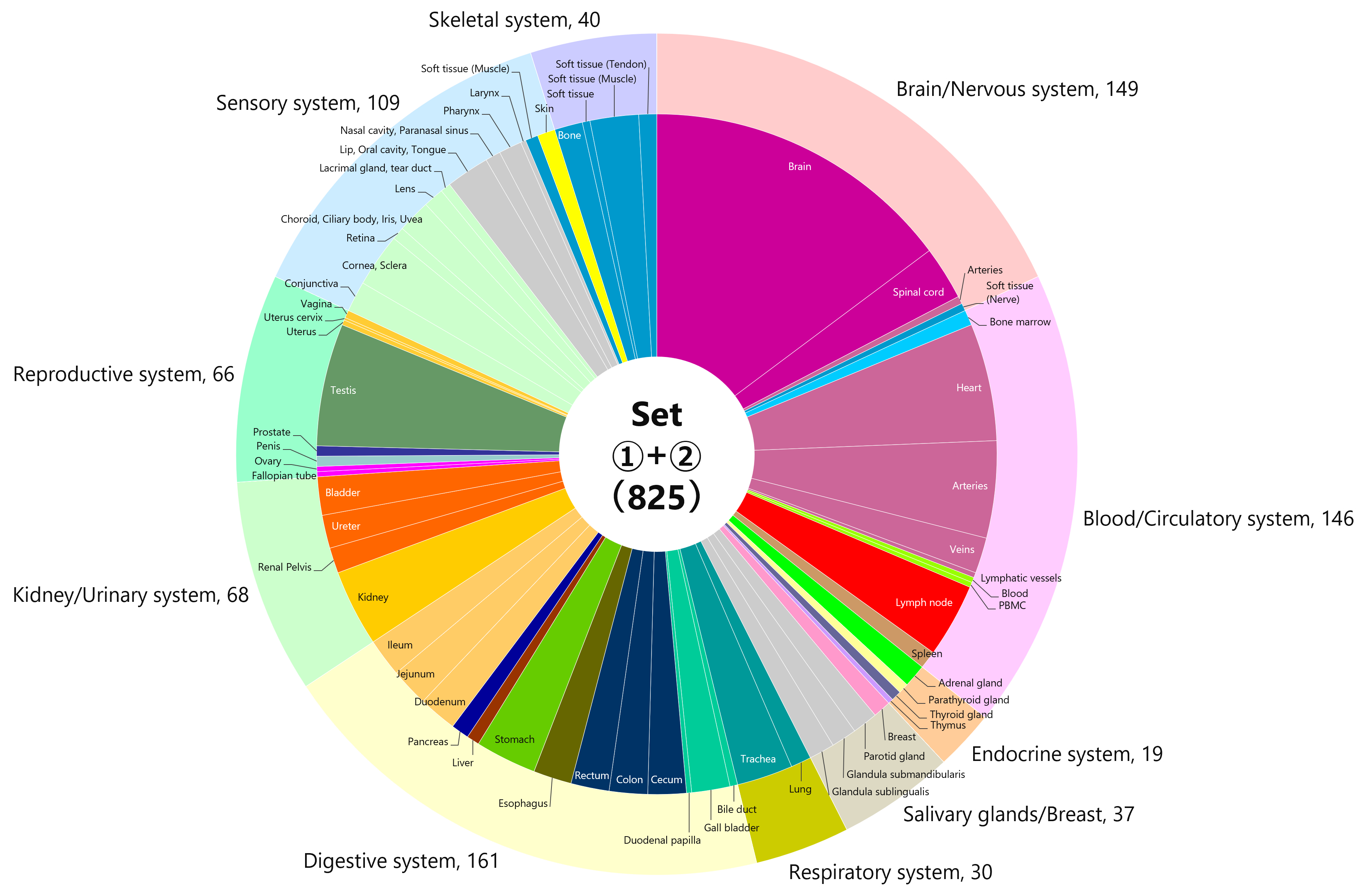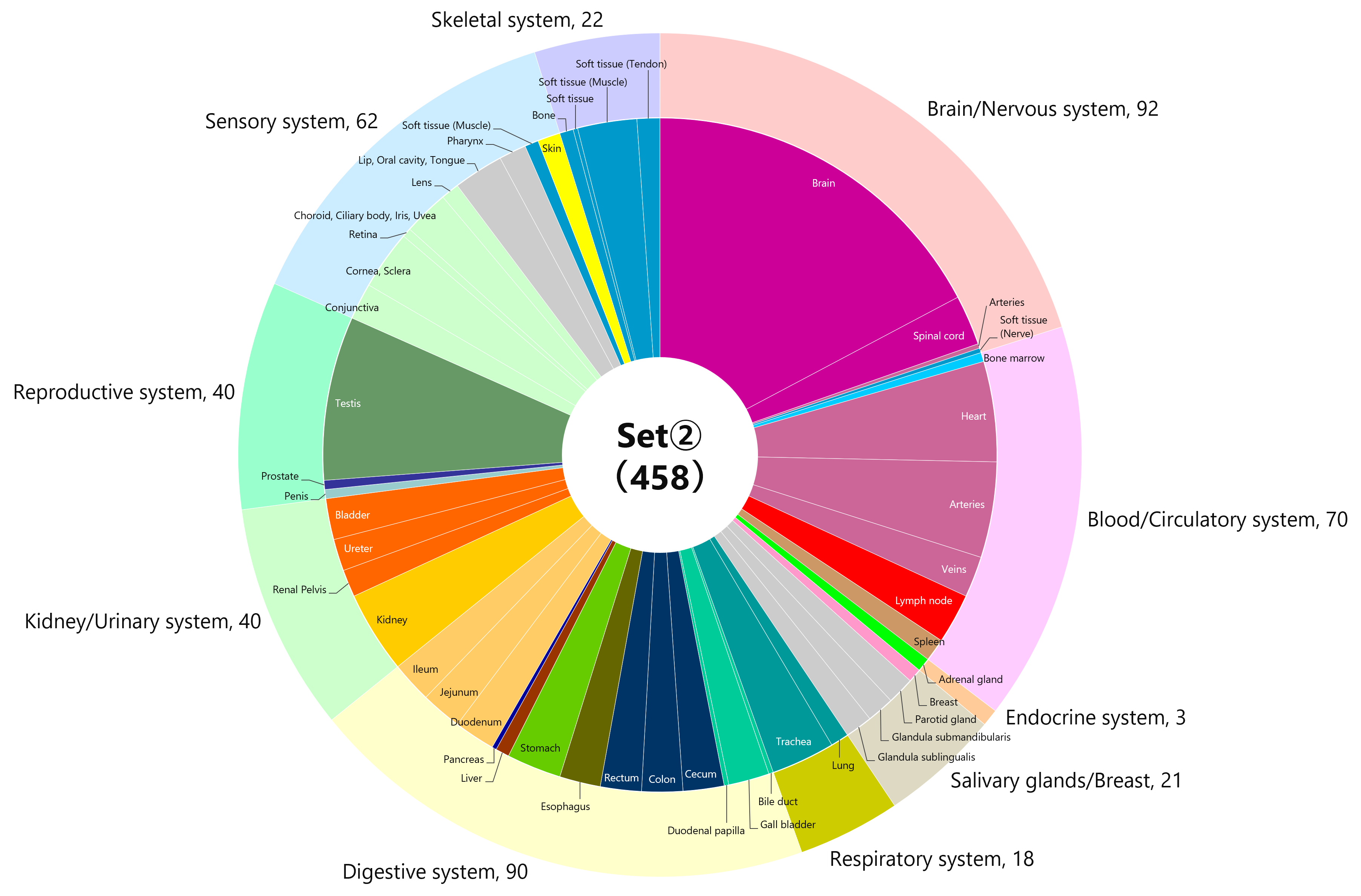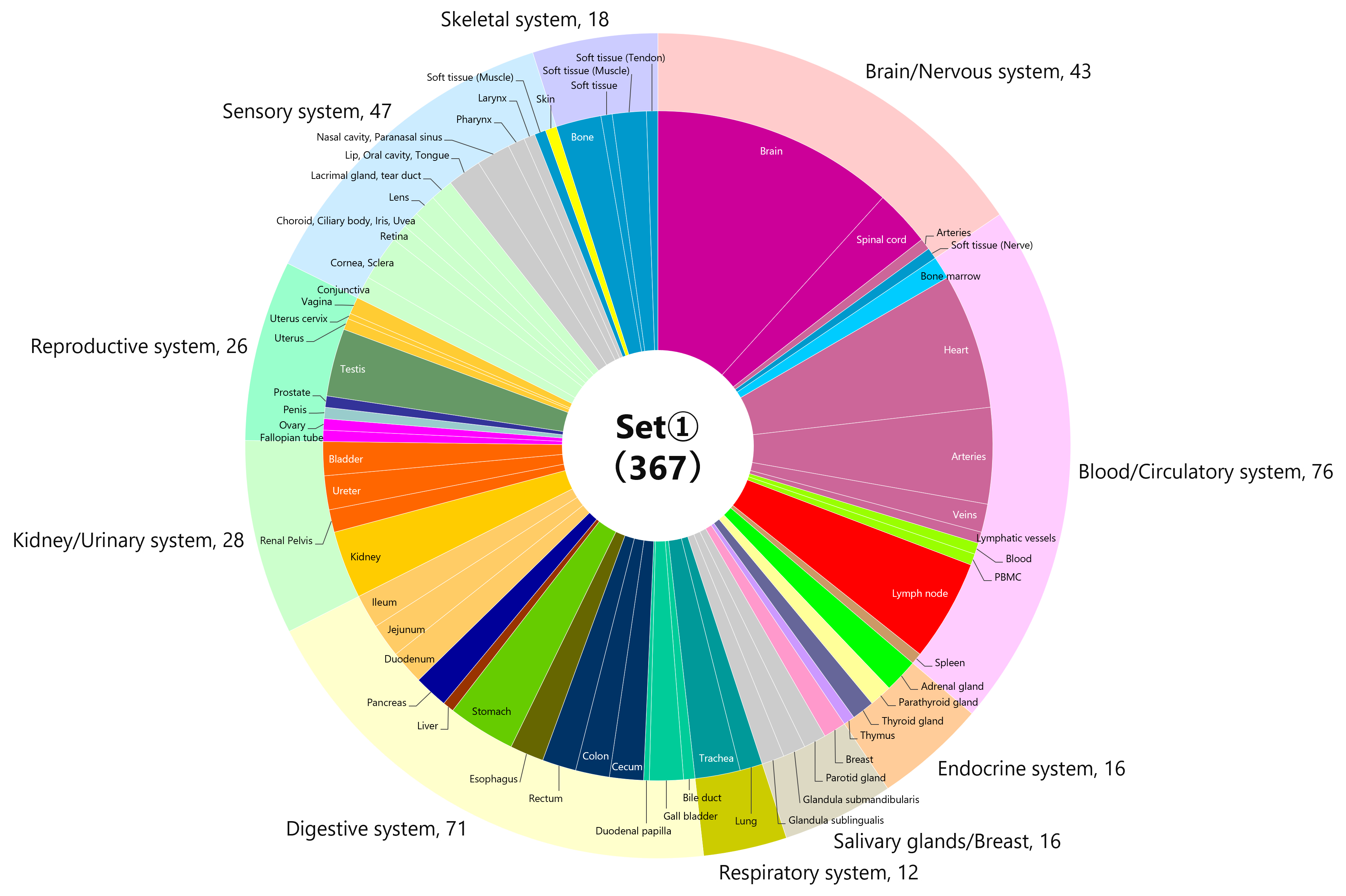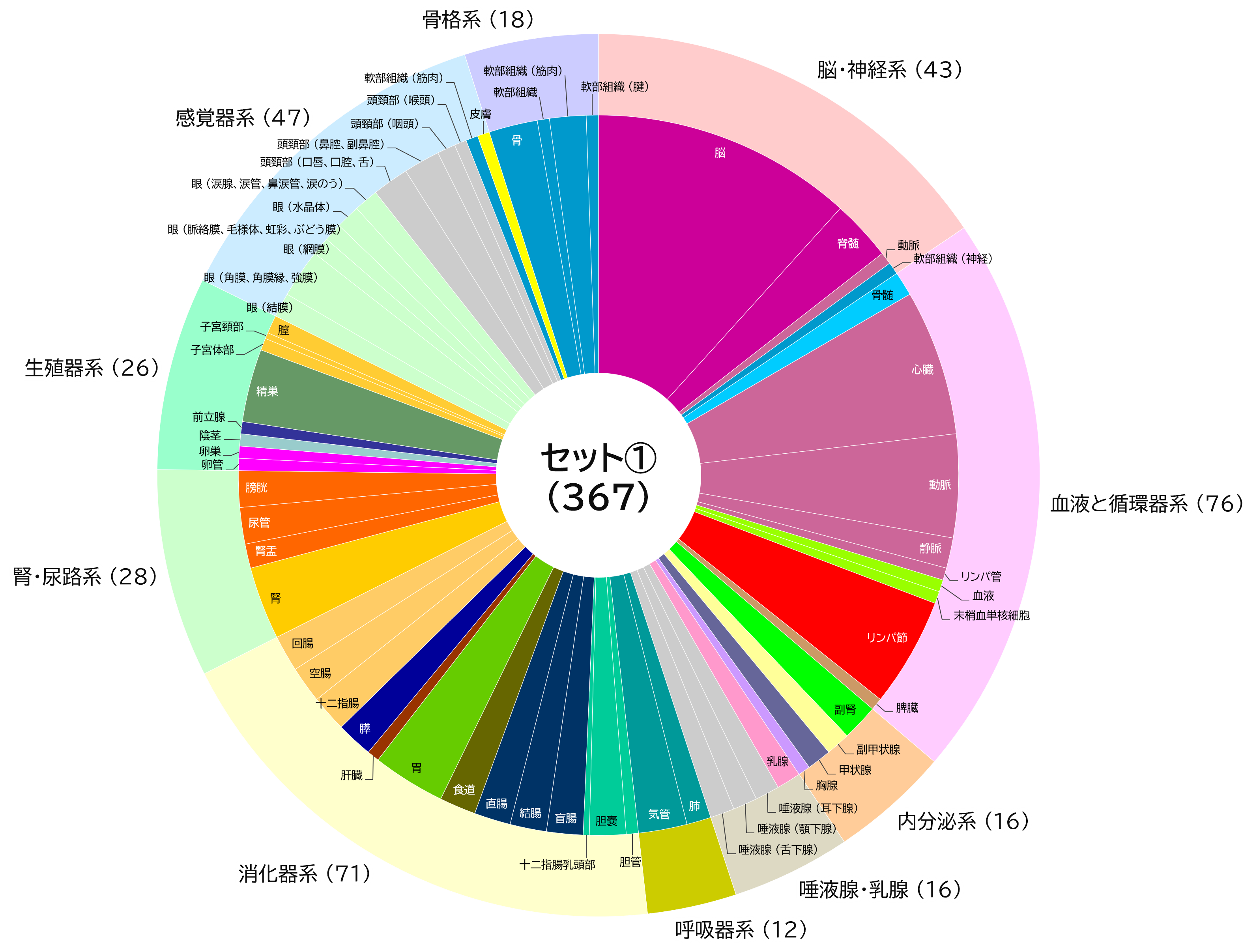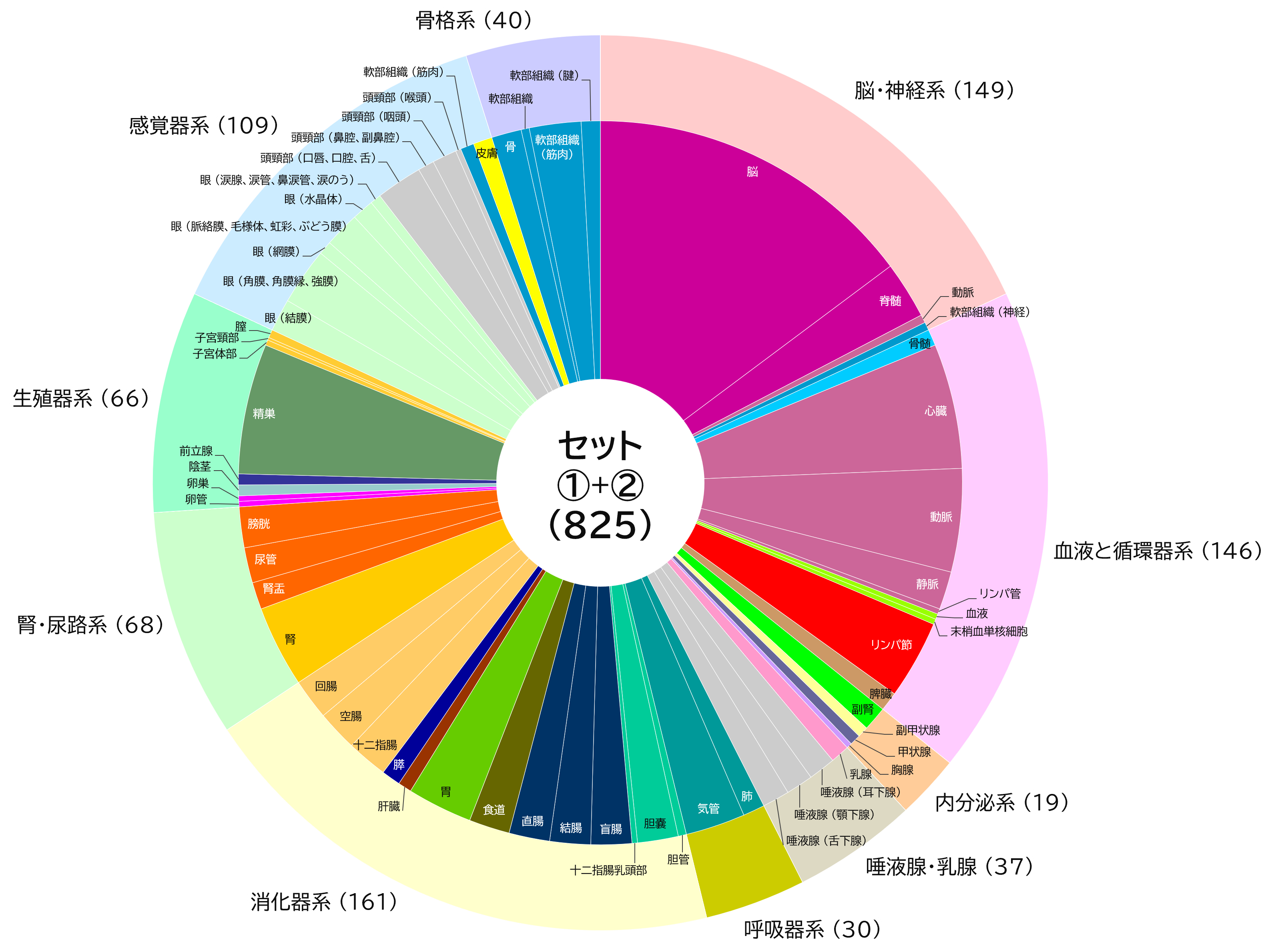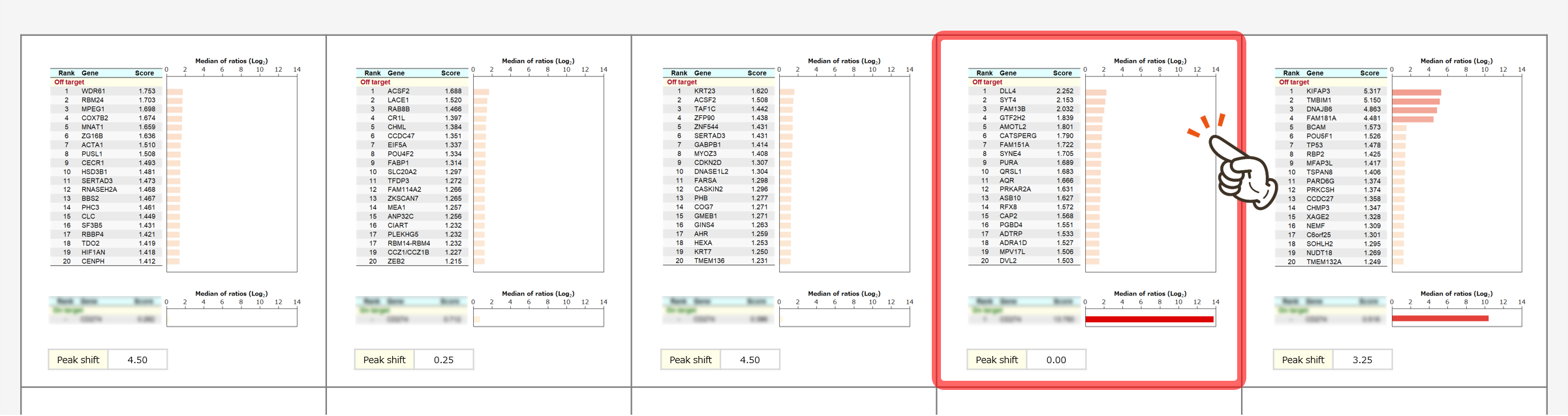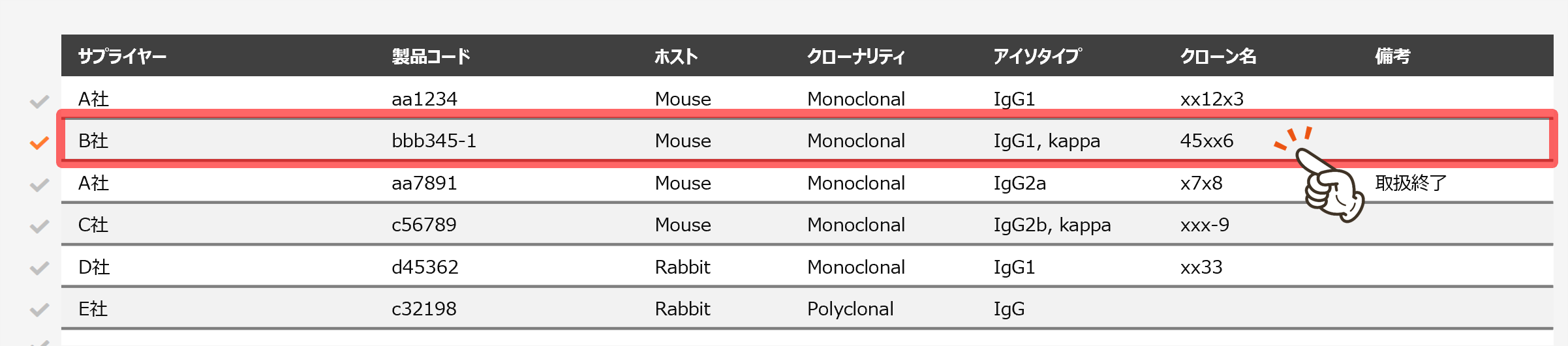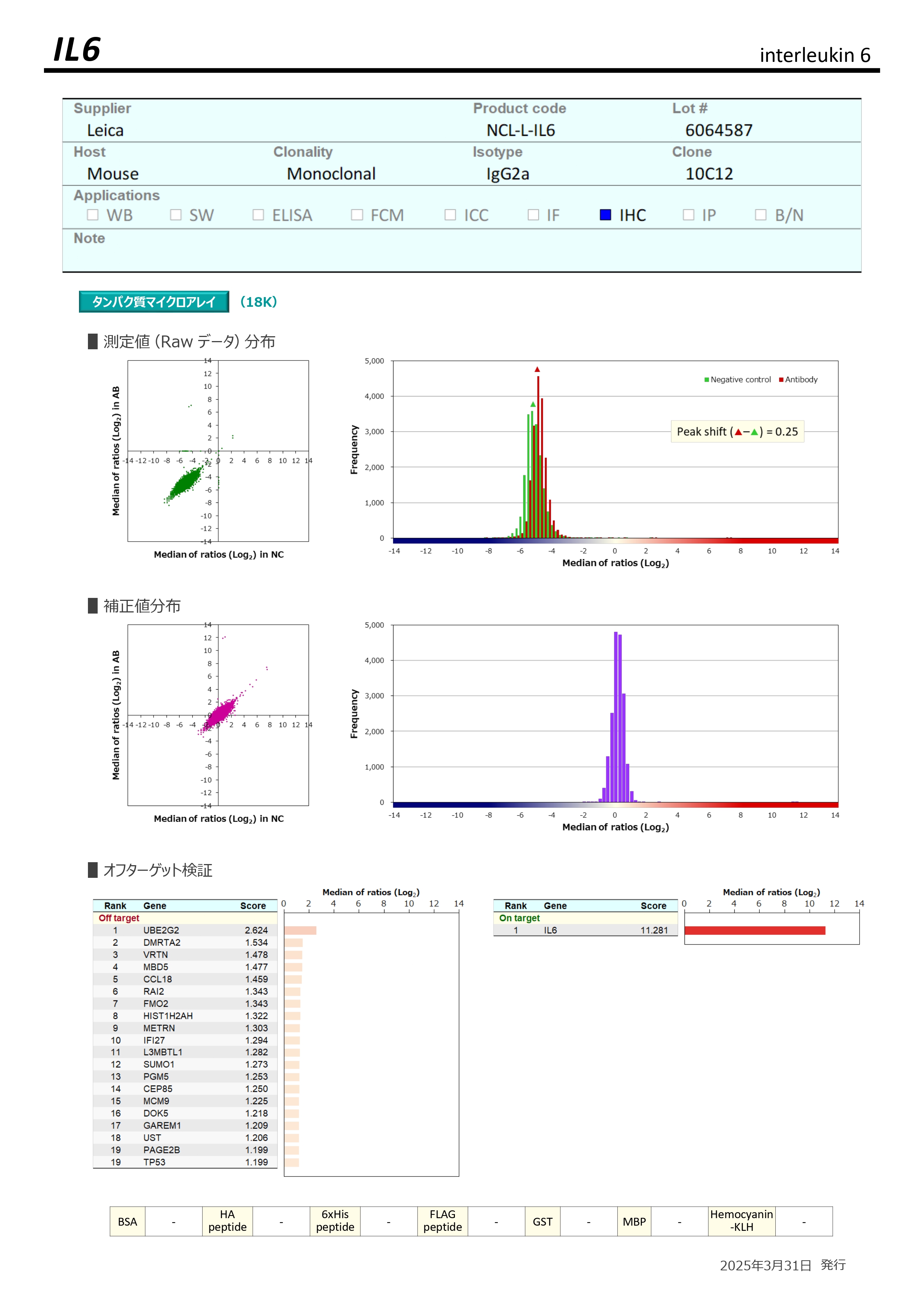こんにちは!
人の細胞には寿命があります。例えば、小腸の上皮細胞の寿命は約1日、皮膚の上皮細胞の寿命は約1か月、赤血球の寿命は約4か月です。細胞の増殖は必要な時に必要な分だけ細胞が増えるようにきちんと制御されていて、私たちの体の細胞は実は知らないうちに入れかわっています。今回は細胞が増える仕組みについてお話します。
細胞が分裂するサイクルを細胞周期といい、その過程を「G1期」、「S期」、「G2期」、「M期」の4つに分けます。この周期をまわることで細胞は分裂します。分裂をいったんやめる細胞はこの周期をはずれて「G0期」に入ります。
G1期は運命の分かれ道です。次のS期に進むのか、細胞周期からはずれてG0期に入るのかを決めるのです。S期でDNAの複製が行われるので、G1期の間にDNAの損傷がないかを確認し、損傷があればDNAを修復します。細胞が成長し、分裂する準備が整うとS期に進みます。
S期はDNA複製期です。DNAの2本鎖がほどかれ、分離したそれぞれのDNA鎖を鋳型とし、相補的なヌクレオチドを結合させていきます。こうして元のDNA鎖1本と新しく作られたDNA鎖1本が結合した2本鎖DNAが2組作られます。
S期の次はG2期です。S期での複製に問題がないかを確認します。問題があればDNAを修復し、問題がなければM期に進みます。
M期は分裂期です。DNAはぎゅっーと凝縮します。凝縮した状態のDNAを染色体といいます。核膜はいったん消失して、染色体が細胞の中央に並びます。その後、細胞の両端に引っ張られるようにして、2組作られたDNAが一組ずつ細胞の両端に移動します。2つに分かれたDNAの周りに再び核膜ができます。最後に細胞の中央にくびれができ、細胞が2つに分かれます。
細胞が分裂する時に、遺伝情報となるDNAを等しく正確に分けることが重要です。そのために、元々あったDNAと全く同じDNAのセットをS期でもう一組作り、それをM期で2つの細胞に分けるという方法をとっているのです。塩基の相補性があるからこそ可能となった方法といえます。