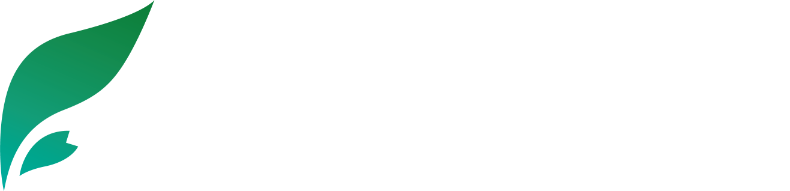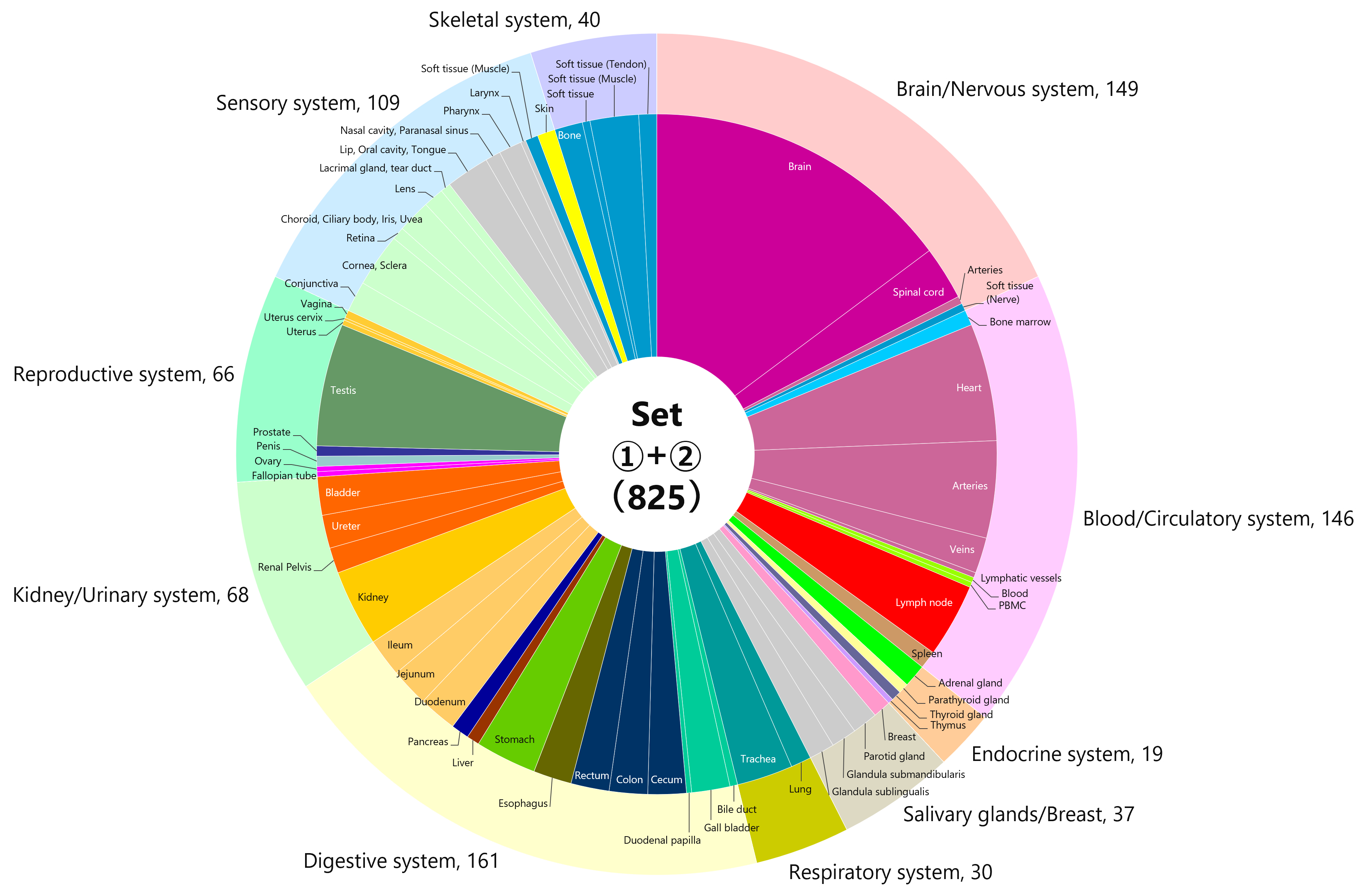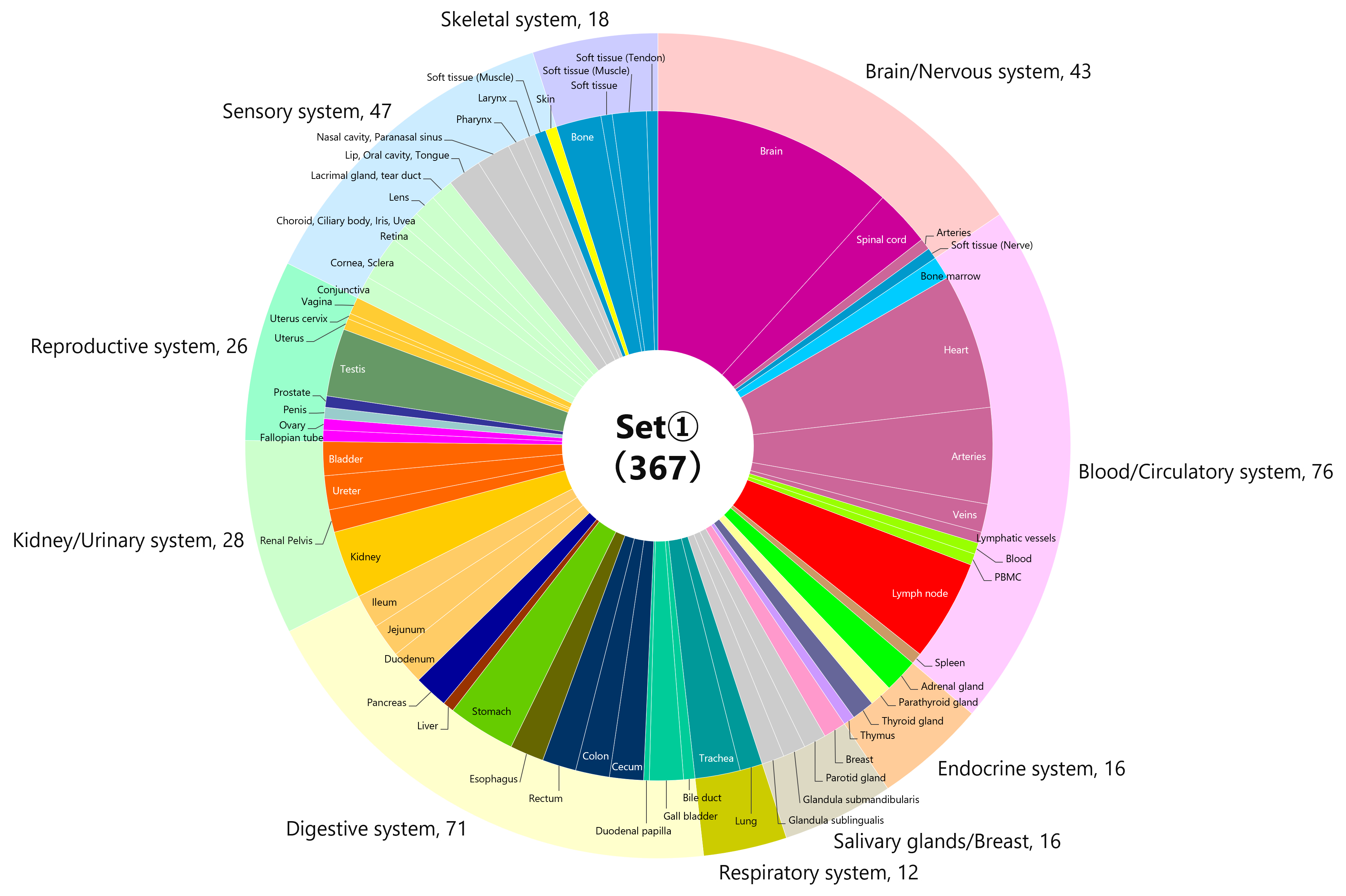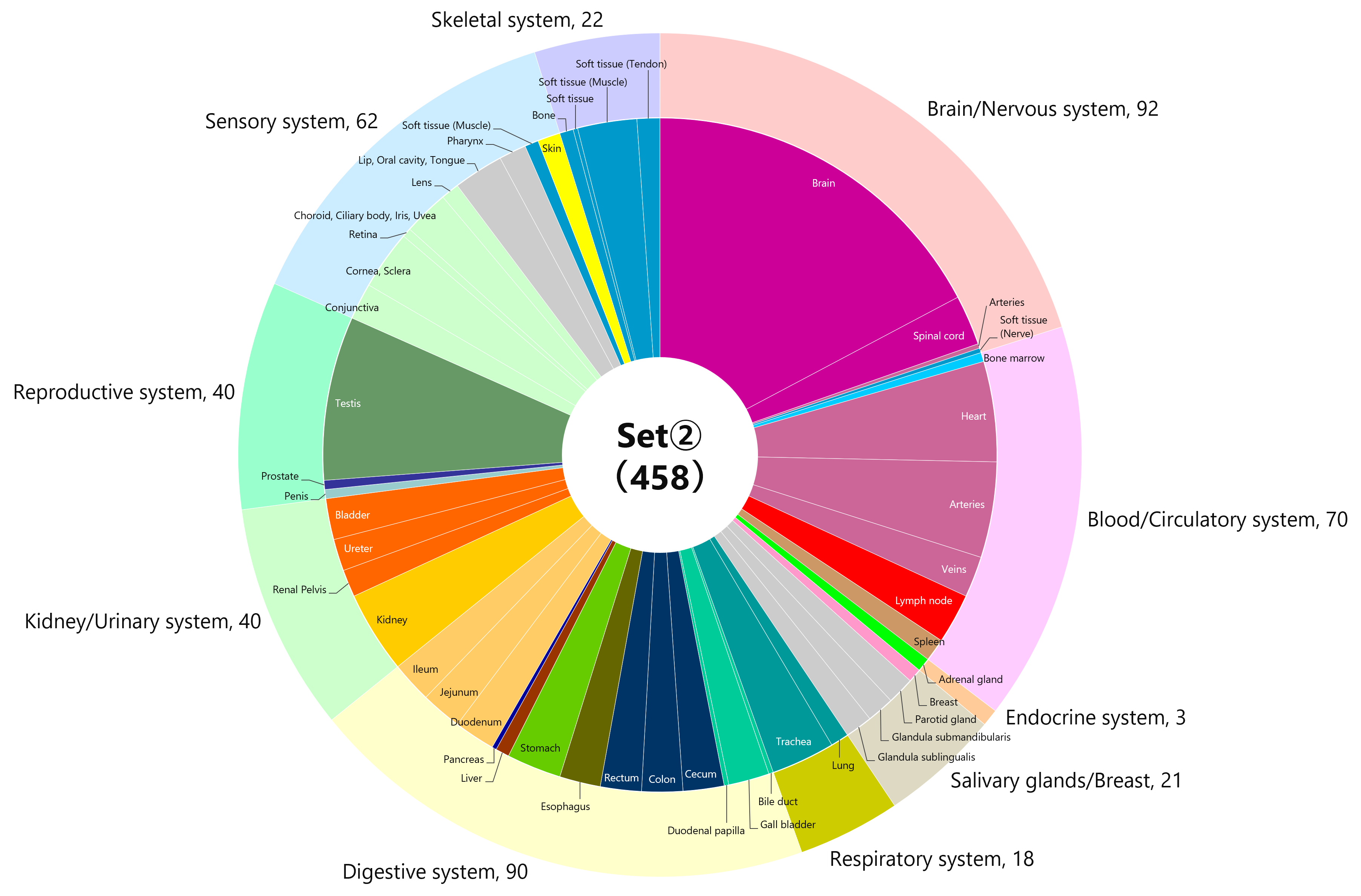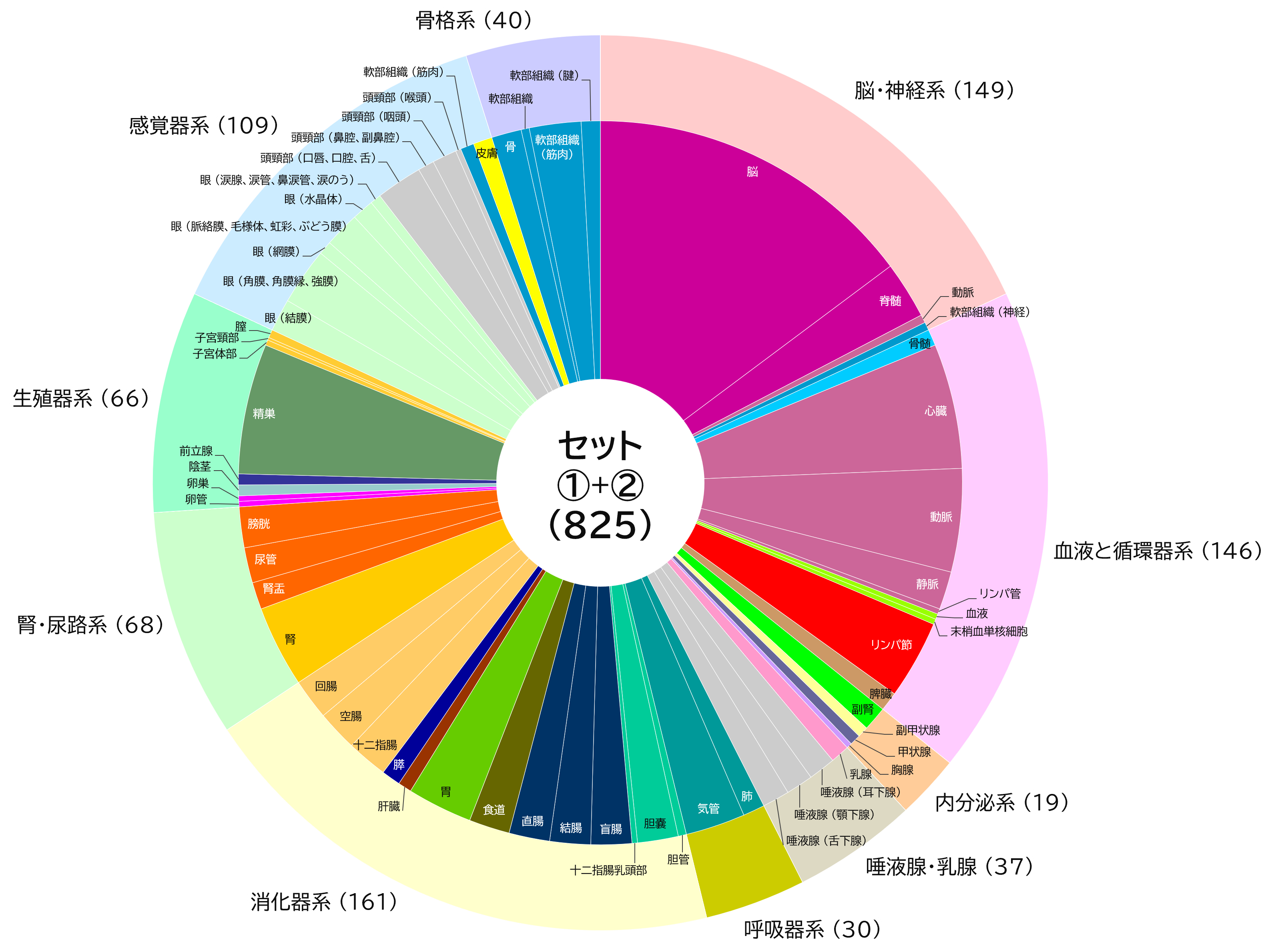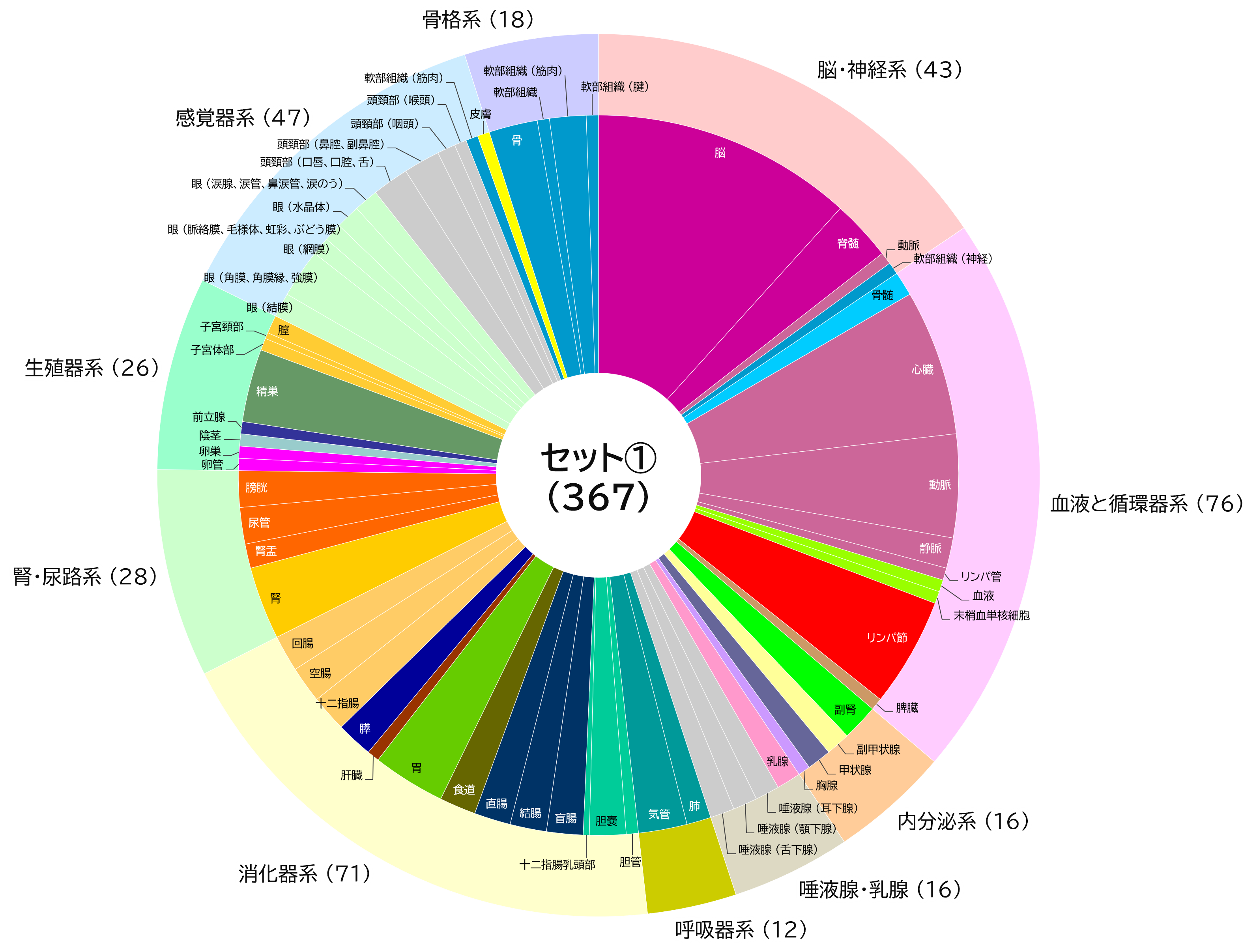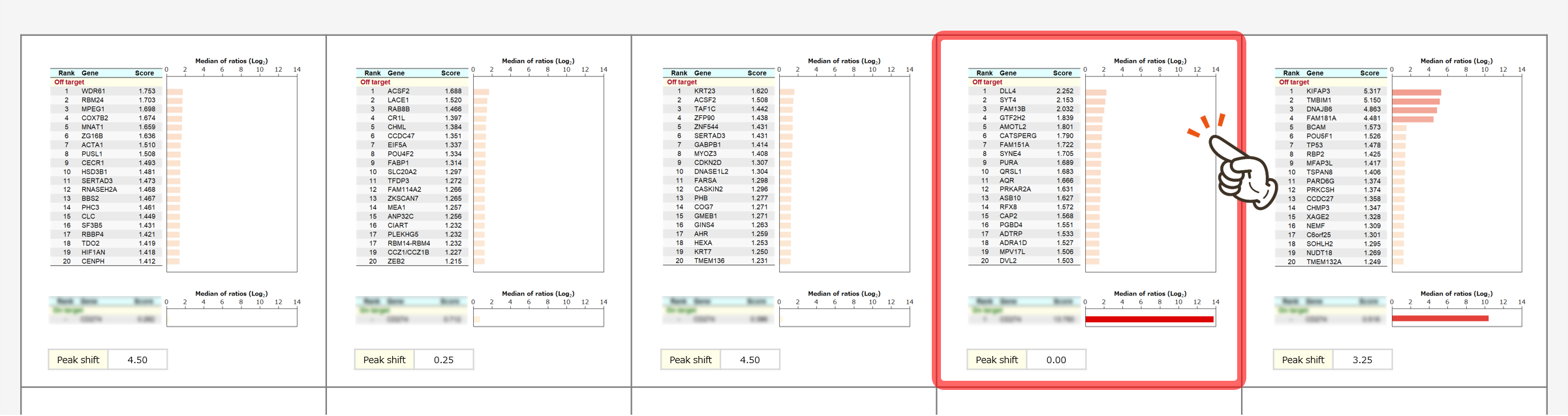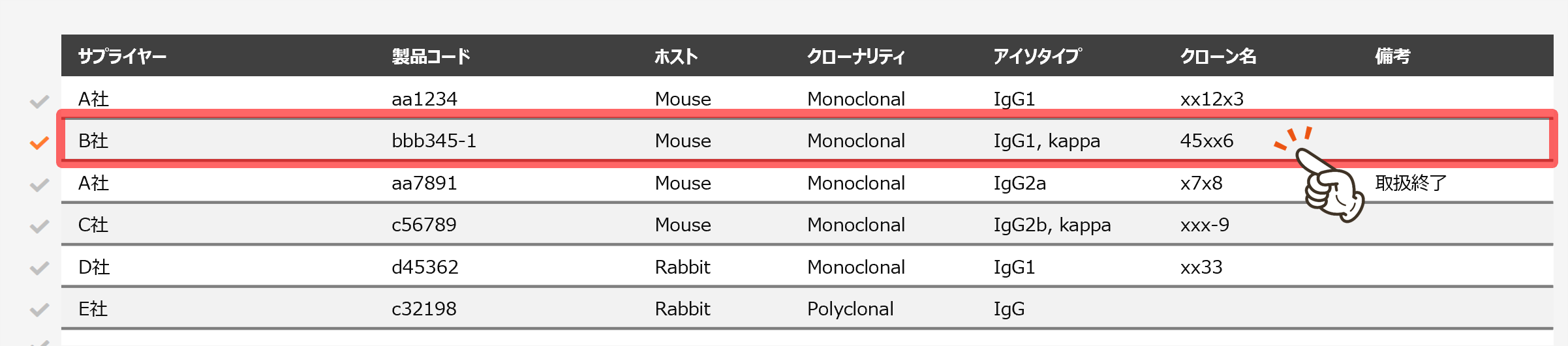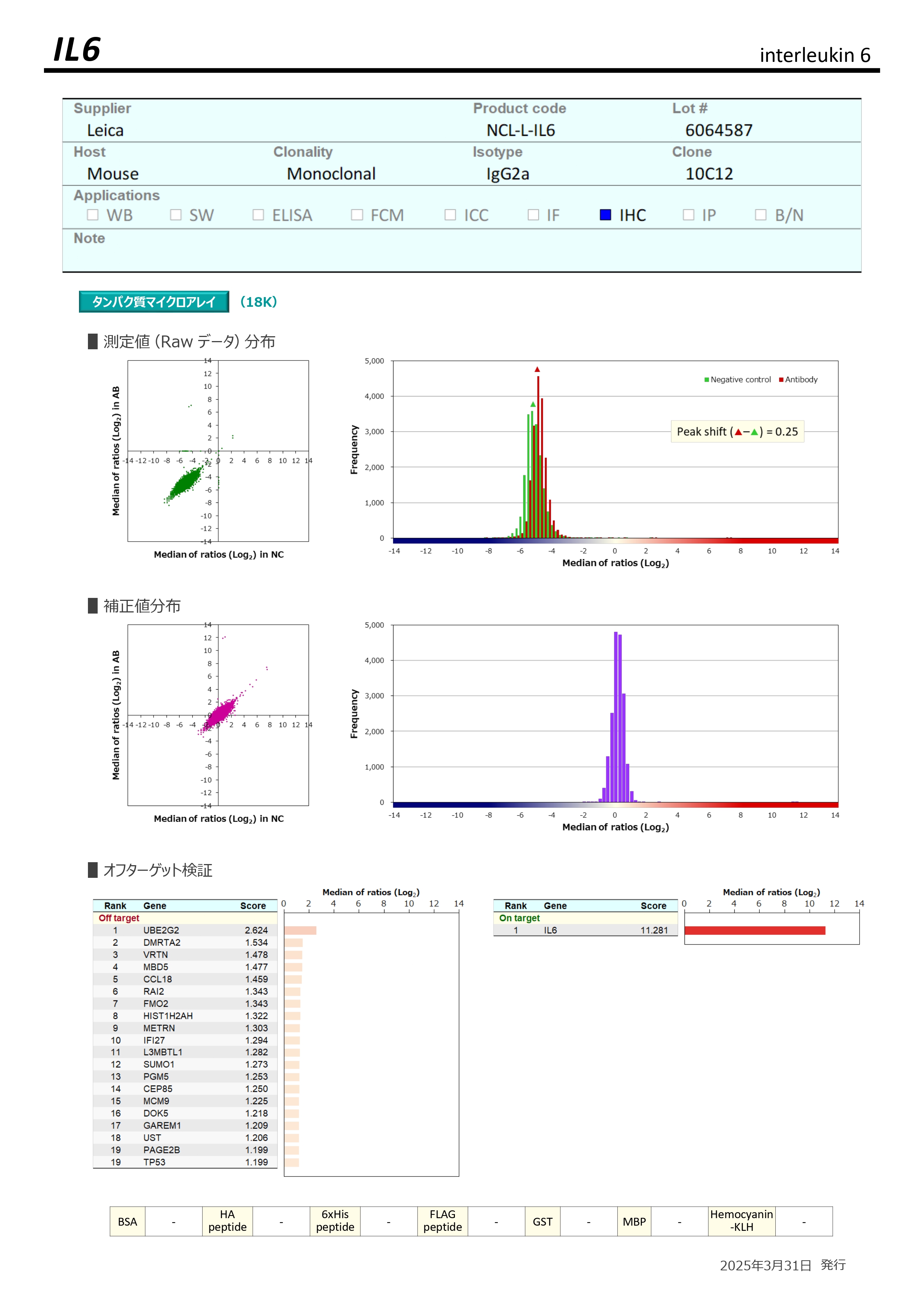こんにちは!
これまでに、肺がんには大きく分けると「小細胞がん」と「非小細胞がん」の2つのタイプがあるというお話をしてきました。でも、肺がんは、実はさらに細かく分類できます。今回は、肺がんの細かい分類についてお話します。
分類というのは、物事を理解しやすくするために、ある基準にもとづいてグループ分けをすることです。肺がんは、以前は形態学的な特徴にもとづいて「小細胞がん」、「腺がん」、「扁平上皮がん」、「大細胞がん」という4つのタイプに分類されていました。非小細胞がんは腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなどのことです。
腺がんは粘液などを分泌する腺上皮に発生するがんです。扁平上皮がんは扁平上皮に発生するがんです。たばこなどの刺激により、気管支の上皮細胞が扁平上皮に変化し(扁平上皮化生)、それががん化したものが肺の扁平上皮がんです。大細胞がんは腺がんや扁平上皮がんや小細胞がんの成分が認められない肺がんで、細胞が大型化したがんです。
しかし、2015年に肺がんの分類が変更されました。これまでは形態学的な特徴で分類していましたが、細胞の性質で分類するという考え方が採用されたのです。細胞の性質で分類する方が病気の性質を理解しやすいですし、治療方針の決定にも役立つからです。この変更により、肺がんの分類は「腺がん」、「扁平上皮がん」、「大細胞がん」、「神経内分泌腫瘍」の4つに分けられ、小細胞がんは神経内分泌腫瘍に含まれることになりました。
神経内分泌腫瘍は神経内分泌細胞から発生するがんです。神経内分泌細胞は特殊な神経細胞で、ホルモンという体の機能を調整する物質を分泌します。肺がんの神経内分泌腫瘍には、小細胞がんの他に「大細胞神経内分泌がん」、「定型カルチノイド」、「非定型カルチノイド」という名前のがんが含まれます。
ちなみに、以前の分類と新しい分類は何を基準にするかが違うだけですので、以前の分類が間違っているということではありません。
次回は、肺がん細胞株のクラスタ解析(解析例1)をして感じたことについてお話させていただきます。